臨床研修施設
獨協医科大学埼玉医療センター
東部
928床
3次救急
JR武蔵野線「南越谷駅」より徒歩3分
臨床研修施設
3次救急
がん拠点・連携
サブスぺ充実
大学院
学会補助有
症例数が多い
託児所有
駅チカ
■症例数がとにかく多い
■色々な大学出身者が集まる
■臨床研修センターのサポートが充実

外科
獨協医科大学埼玉医療センター外科専門医養成プログラム
外科
獨協医科大学埼玉医療センター外科専門医養成プログラム
外科
獨協医科大学埼玉医療センター外科専門医養成プログラム
年間1000件超のロボット手術&緊急手術 多彩な症例を経験しスキルを磨く
年間手術件数1000件超の獨協医科大学埼玉医療センターで外科専門医を目指す小林先生。「圧倒的な手術件数と幅広い症例を経験できることが決め手になった」と話す専門研修プログラムの内容を詳しくお聞きします。
取材日:2023年11月
更新日:2025年04月

小林 峻也こばやし たかや
医師期間
専攻医2年目(医師4年目)※取材当時
出身大学
獨協医科大学
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
ロボット手術や緊急手術など手術件数は年間1000件超
大学で実習していた頃に外科の楽しさを知り、臨床研修でこちらに来た時に医局の雰囲気のよさを感じて外科に入局、プログラムへの参加を決めました。当センターには「ダビンチ」や「hinotori」といった手術支援ロボットが導入されており、最先端の低侵襲手術からcommon diseaseまで多彩な症例を経験できる点が魅力だと思います。手術件数は1年間で1000件を超え、連携医療機関も多数あるので幅広く経験を積める環境が整っていると言っていいでしょう。今はまだ基本の「キ」の部分を学んでいる段階ですが、高難度の手術をこなす先輩方を見習って、自分自身のスキルを高めていきたいと思っています。

上部消化管・下部消化管・肝胆膵を中心に必要症例を網羅
所属している外科は上部消化管・下部消化管・肝胆膵と3チームに分かれていて、初年度は3カ月毎にローテーションで各チームを回りました。2年目の今年は千葉徳洲会病院に3カ月間の研修に行き、今は肝胆膵チームの一員として仕事をしています。当センターには外科以外に呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺科などが一通りそろっているので、1つの病院で必要な症例をもれなく経験できるのではないかと思います。同期の人数も多く、それぞれがいろいろな科に散らばっているので、科をまたいで相談しやすいことも助かっています。変な上下関係もありませんし、休みもしっかり取れるので、同期のみんなで「悪いところは見当たらない」と自負しています(笑)。

患者さんの元気な姿を見られることが外科医としてのやりがい
担当患者さんは少ない時で10数人、MAXで40人くらいなので、平均すると20~30人程度といったところでしょうか。これまでに胆嚢炎やヘルニアといったよくある疾患から、悪性疾患や緊急手術などを幅広く経験してきました。今も心に残っているのは、大腸癌の手術を前にして「人生なんてどうでもいい」と投げやりになっていた患者さんです。自分が執刀した手術は無事に終わり、退院後しばらくして外来にお越しになったのですが、何だか見違えるようにお元気になられていて。「第二の人生が始まったわ」とハツラツとしたお姿を見られたことが、最近のほっこりするエピソードです(笑)。多忙なイメージのある外科ですが、当センターは有休のほかに育休・産休もしっかり取れる“ホワイト”な職場ですから、ぜひ一度見学にいらしてください。

 1日のスケジュール
1日のスケジュール
08:00
出勤、術前検討(週2回)
08:30
チーム回診
08:45
手術または病棟業務
※日中の業務は日によって異なる
18:00
外科カンファレンス(週1回)
18:00
退勤
※手術などによって退勤時間が遅くなることもある

内科
獨協医科大学埼玉医療センター内科専門医プログラム
内科
獨協医科大学埼玉医療センター内科専門医プログラム
内科
獨協医科大学埼玉医療センター内科専門医プログラム
アブレーション、デバイス、TAVI…。三次救急だからできる貴重な経験
臨床研修を通して「急性期医療に携わりたい」という思いを強くし、循環器内科を選択した新井先生。獨協OGでもある新井先生がプログラム選びで重視したポイント、今も心に残るエピソードなどをお聞きしました。
取材日:2023年11月
更新日:2025年04月

新井 澪奈あらい みおな
医師期間
専攻医2年目(医師4年目)※取材当時
出身大学
獨協医科大学
お住まい
越谷市
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
豊富な症例数と充実の指導体制がプログラム選びの決め手
循環器内科は心臓や血管の病気を扱い、心筋梗塞などで運ばれて来る患者さんに対してカテーテル治療などを行います。臨床研修の時、救急車で運ばれて来た患者さんが治療によってすっかり元気になってお帰りになる様子を目の当たりにして、急性期疾患を診たいと強く思うようになりました。こちらのプログラムを選んだのは、私が獨協大学出身ということに加えて、アブレーションやデバイスといった高度な医療を実践していることが決め手でした。高い専門性を持った指導医も多くいらっしゃるので、ここでならたくさんのことを学び、さまざまな症例を経験できると思ったのです。実際に1年目は虚血、不整脈、ストラクチャーのほかに救命救急も回り、2年目の今は循環器内科で担当する症例を幅広く診ています。

三次救急だから経験できるアブレーション、デバイス、TAVI
これまでに経験した症例としては、狭心症、心筋梗塞、不整脈、心臓弁膜症、心不全などで、季節の変わり目や寒い時期になると患者さんの数が増える印象です。当センターは三次救急医療機関のため、致死率の高い心筋梗塞などで運ばれて来る患者さんも多く、二次救急では経験できないアブレーション、デバイス、TAVIなどの技術を習得できる点が魅力です。私も初めて重症例を担当した時のことはよく覚えていますが、心室細動で意識のなかった患者さんに対してカテーテル治療を行い、リハビリを経て患者さんが歩いてお帰りになった時には、何ともいえない充実感がありました。今も平均して5~6人の患者さんを受け持っていますが、急性期から慢性期まで幅広い症例を経験できることも当センターならではだと思います。

産休・育休・時短勤務もOKな働きやすさも魅力
毎朝8時半から始まるカンファレンスで1日がスタートし、その後はカテーテル検査や治療などを行い、夕方の回診を終えると6時頃には業務終了となることが多いです。当直は月に3~4回ほど、オンコール当番は事前に予定が分かっているので、その日だけ携帯を気にしながら過ごす…という感じです。当センターの先生方はみなさん優しい雰囲気の方が多く、同じ科はもちろんほかの科とのコミュニケーションも良好なので、どんなことも相談しやすくて助かっています。今のところ私が期待していたとおりに幅広い症例を経験できていて、不満に思うことは特にありません。産休や育休はもちろん、子育て中の時短勤務もOKなので、ライフステージの変化があっても働きやすいのではないかと思います。

 1日のスケジュール
1日のスケジュール
08:30
出勤、カンファレンス
09:00
病棟業務、外来、カテーテル検査・治療
13:30
病棟業務、カテーテル検査・治療、超音波検査
17:00
~18:00 退勤

泌尿器科
獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科専門研修プログラム
泌尿器科
獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科専門研修プログラム
泌尿器科
獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科専門研修プログラム
腎移植や小児泌尿器疾患をはじめ専門性の高い症例を幅広く経験
男性・女性を問わず、小児から高齢患者まで幅広い症例を経験できることに面白さを感じて泌尿器科を選んだという池添先生。多くの手術を手がける日々の様子や今後のキャリアプランなどについてお聞きしました。
取材日:2023年11月
更新日:2025年04月

池添 慧梨香いけぞえ えりか
医師期間
専攻医2年目(医師4年目)※取材当時
出身大学
香川大学
お住まい
最寄り駅:東川口駅
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
腎臓・膀胱・尿管・尿道…多岐にわたる診療領域
臨床研修でいろいろな科を経験したとはいえ、2年間で自分の専門を決めることはなかなか難しいことでした。そうした中で泌尿器科を選んだのは、悪性腫瘍から排尿障害まで多彩な疾患を扱い、子どもから高齢の方まで幅広い年齢層の患者さんを診られることが決め手でした。一口に泌尿器といっても、診療領域は腎臓・膀胱・尿管・尿道など多岐にわたります。幅広い症例を担当するうちに、いつか自分が興味の持てる分野が見つかるかもしれない…。そんな期待もあってプログラムに応募しました。以前こちらに見学に来たとき「症例数の豊富さが強み」との説明を受けましたが、実際に仕事をしてみて本当にその通りだなと実感しています。腎移植や小児泌尿器疾患、ロボット手術などを経験できることも当センターならではだと思います。

腎移植や小児泌尿器疾患など専門性の高い症例を経験
毎朝回診を終えると手術、お昼を食べて午後も手術という感じで、専攻医1年目からたくさんの手術を執刀させてもらってきました。腎移植などは術前・術後の管理に加えて患者さんのメンタルケアを担う必要もあり、多くのことを学ぶことができています。また、腎移植や小児の泌尿器疾患は専門医取得に必須の症例だと聞いていますので、このプログラムを選んで間違いなかったと思います。当センターは臨床だけでなくアカデミックな面にも力を入れていて、初年度から学会に参加したり、論文を執筆したりと、しっかり勉強させていただいています。上の先生方も面倒見のいい方ばかりで、「勉強をしたい」という希望も「休みを取りたい」というお願いも、しっかり受け止めてくださるのでありがたいです(笑)。

多彩な手技を身につけることが自分の武器になる
印象に残っている症例は、治療がうまくいかなかったケースが多いのですけれど。女性患者さんから「女性の先生で良かった」「同じ女性だから話しやすい」などと言っていただけると、「私がここにいた甲斐があったな」とうれしく思います(笑)。今は専攻医2年目で、来年は研修先を関連病院に移すことになります。その先のキャリアプランはまだ考え中ですが、家庭中心の働き方にシフトしても、バリバリ仕事をするにしても、泌尿器科の多彩な手技を身につけることは大きな武器になると思っています。当センターは泌尿器疾患の症例が豊富で、若手でも多くの手術を任せてもらえます。症例に対して医師が足りないくらいなので(笑)、ぜひ一人でも多くの方に仲間になっていただきたいです。

 1日のスケジュール
1日のスケジュール
07:45
出勤
08:00
病棟回診
毎日チームで病棟回診をします。月曜・水曜はカンファレンスがあり、その後病棟回診を行います。
08:30
手術・患者処置
担当症例の手術に入ったり、病棟・外来の患者処置を行います。
12:00
昼休み
13:00
手術・患者処置
担当症例の手術に入ったり、病棟・外来の患者処置を行います。
17:00
病棟回診
チームで病棟回診をします。月曜は科内カンファレンスを行います。
18:00
退勤
 経験症例
経験症例

耳鼻咽喉科
獨協医科大学埼玉医療センター耳鼻咽喉科専門医養成プログラム
耳鼻咽喉科
獨協医科大学埼玉医療センター耳鼻咽喉科専門医養成プログラム
耳鼻咽喉科
獨協医科大学埼玉医療センター耳鼻咽喉科専門医養成プログラム
上級医の指導のもと数多くの手術を執刀し、首から上を全て診る
子どもの頃から医療が身近なところにあり、自身のアレルギー体質などもあって耳鼻咽喉科を選択したという田中先生。「デメリットを感じたことがない」と話す専門研修プログラムの魅力をお聞きします。
取材日:2023年11月
更新日:2025年04月

田中 星有たなか せいあ
医師期間
専攻医2年目(医師4年目)※取材当時
出身大学
鳥取大学
お住まい
賃貸マンション
将来の目標
アレルギー専門
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
耳・鼻・喉…首から上の領域を全て診る
両親が医療従事者のため、小さな頃から医療の仕事に興味を持っていました。中でも耳鼻咽喉科は聴覚・嗅覚・味覚など私たちのQOLに直結する器官を扱う診療科です。病気に対して内科・外科の両方からアプローチできることにも魅力を感じて、耳鼻咽喉科に進むことを決めました。当センターには臨床研修でもお世話になりましたが、その時も上級医が非常に丁寧に指導してくださり、学会発表などもさせていただきました。耳鼻咽喉・頭頸部外科という名前のとおり耳、鼻、口頭・咽頭、頭頸部の疾患をまんべんなく診られて、学会や手術研修会などでインストラクターを務める先生方がそろっている……そういったところが決め手になってこちらのプログラムを希望しました。

上級医の指導のもと数多くの手術を執刀
これまでに経験した症例としては、慢性扁桃炎や小児の睡眠時無呼吸症候群に対するアデノイド切除術・口蓋扁桃摘出術などが挙げられるでしょうか。これらの手術は若手医師の登竜門ともいわれるものですが、上級医の指導のもと専攻医1年目から手術を執刀し、2年目の今は週に3日手術を担当しています。私はアレルギーに興味があって、将来は鼻科を専門にしてアレルギーを深く学びたいと思っているので、鼻科領域の症例を数多く経験できることはとてもありがたいです。自分の手術によって「子どものいびきがまったく無くなりました」「手術を受けて良かったです!」と喜んでくださるご両親の声を聞くたびに、うれしい気持ちでいっぱいになります。

女性医師が多数活躍し、休暇制度も充実
耳鼻咽喉・頭頸部外科には女性医師が多く在籍していて、育休中の先生や出産後に時短勤務で働いている先生もいます。また、奥様の出産後しばらく出産休暇を取った先生もいたりするので、休暇制度はしっかりしていると思います。当直は月に4回ありますけれど、有休も取りやすいので「忙し過ぎて勉強する時間がない…」ということはありません。手術がある日は帰宅時間がずれ込むこともありますが、平均して午後6時には業務終了となることが多いです。その道のスペシャリストといえる先生方に教えていただけて、手術もたくさん経験できて、お休みなどの面も不満がなくて。本当に「ここに入って良かった」と思っていますし、今のところ悪いところは見つけられません(笑)。

 1日のスケジュール
1日のスケジュール
08:00
出勤
08:30
手術、外来、病棟処置、病棟回診
※手術日:火・木・金
14:00
手術、外来、病棟回診、カンファレンス
※手術日:火・木・金 ※カンファレンス:火曜日の夕方
18:00
退勤

眼科
獨協医科大学埼玉医療センター眼科専攻医プログラム
眼科
獨協医科大学埼玉医療センター眼科専攻医プログラム
眼科
獨協医科大学埼玉医療センター眼科専攻医プログラム
症例数が豊富で、眼科手術の経験を積みたい人には理想的な環境
獨協医科大学出身で、初期研修に続き、眼科の専門研修プログラムも母校を選んだ川久保先生。手術の症例数が多く、幅広い経験ができることに魅力を感じたと言います。眼科ならではのやりがいや、将来のビジョンなどを伺いました。
取材日:2024年2月
更新日:2025年04月

川久保 慧かわくぼ さとし
医師期間
専攻医2年目 医師4年目※取材当時
出身大学
獨協医科大学
お住まい
埼玉県 越谷市
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
専攻医1年目から多様な疾患に対応、200症例の手術を経験
眼科を選んだのは、実家が眼科を開業している点も大きいのですが、初期研修でいろいろな診療科を回る中で、治療によって患者さんの悩みが改善して、元気になって帰ってもらえる機会が他科より圧倒的に多いのがいいなと思いました。私は獨協医大出身で、こちらの眼科は症例数が多く、いろいろな経験が積めることは知っていましたので、専門研修プログラムも迷わずここを選びました。実際に入ってみると、専攻医1年目から白内障や眼瞼下垂を中心に多様な疾患に対応し、約200症例の手術を経験させていただきました。2年目の今年は、その倍の400~500症例を任されています。これほど多くの手術を担当させてもらえる研修施設は、他にはあまり聞いたことがなく、こちらを選んでよかったと改めて思っています。

眼からくる不定愁訴にも、丁寧に対応できる眼科医を目指す
手術は毎週月曜日に3件、火曜日に4件など、週に約7件の手術を継続的に実施しています。私は眼科を選んだ時から「自分の手で治したい」気持ちが強く、手術に興味があったので、今の環境はまさに理想的です。手術の他にも、毎日9時から外来があり、月・火は外来の合間に手術の予定を組んでいきます。眼科の手術はうまくいけば10~15分で終了し、術後は見える世界が大きく変わります。そのため、患者さんから感謝されることが多く、こうした手術に携われることを誇りに思っています。一方で、目の表面も奥も悪くないけれど、なんとなく目の奥が痛いなど、眼科は不定愁訴が多い科でもあります。そうした訴えにも自分なりの答えをもってアドバイスできるように、日々の外来では患者さんの声に丁寧に耳を傾けるように心がけています。
後進の指導・教育にも興味、手術の質の向上にも注力したい
手術に関しては、白内障手術の精度を上げることが今の目標です。白内障手術は、こだわりだしたらきりがないのですが、自分なりの理想形があるので、そこに近づけるために、一つひとつの手術の細部にまでこだわって質の向上を目指します。日々多くの経験ができる分、忙しいですが、残業が特に多いわけではありません。当直も月4回程度ですので、ワークライフバランスは保たれていて、働きやすいです。今後は、硝子体手術を自己主導で執刀できるようにしっかり経験を積み、将来的には実家に戻って眼科医院を継ぎたいと考えています。ただ、それはまだ先の話で、後進の指導や教育にも個人的に興味があります。当科は時間帯を問わず、いつでも指導医の先生方に相談できる環境で、いつもお世話になっていますので、自分もいつか貢献できる側に回れればいいなと思います。
 1日のスケジュール
1日のスケジュール
08:30
出勤 担当患者診察
2-8人ほど
09:00
外来 手術
担当の手術があれば手術 なければ外来
12:00
食事
13:00
午後外来 手術
担当の手術があれば手術 なければ外来
16:30
外来終了
17:00
退勤
 経験症例
経験症例

整形外科
獨協医科大学埼玉医療センター整形外科専門医養成プログラム
整形外科
獨協医科大学埼玉医療センター整形外科専門医養成プログラム
整形外科
獨協医科大学埼玉医療センター整形外科専門医養成プログラム
運動器疾患・外傷を中心に多彩な症例を経験し、専門医取得を目指す
自身の治療体験をきっかけに医師を志したという藤岡先生。同センターでの初期研修を経て整形外科の専門研修プログラムに取り組む藤岡先生に、整形外科医としてのやりがいや現在の働きぶりなどを伺います。
取材日:2024年3月
更新日:2025年04月
藤岡 将史ふじおか まさし
医師期間
専攻医3年目(医師5年目)※取材当時
出身大学
群馬大学
お住まい
埼玉県
将来の目標
専門医取得、専門班での手技獲得
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
患者さんを笑顔にできることが整形外科医のやりがい
僕が医師になりたいと思ったのは、けがをした時に整形外科手術を受けたことがきっかけでした。初期研修でいろいろな科を経験してもやはり、外来・手術ともに整形外科が一番楽しく感じられ、この道に進むことを決めました。また僕自身もですが、もしも「患者さんの死に立ち会うのはちょっと…」と考えているなら、整形外科がおすすめかもしれません。整形外科は主に運動器疾患の治療を担当するので、患者さんは頭や体がお元気な方がほとんどです。自分の治療によって「歩けるようになりました」と喜んでくださると、こちらまで嬉しくなります。患者さんがお元気になり、明るい笑顔で病院を後にする様子を見られることは、整形外科医ならではのやりがいと言えるでしょう。

埼玉県内複数の医療機関を回り、多彩な症例を経験
僕は初期研修もここだったので同期や知り合いもいて、働きやすい環境であることはよく分かっていました。その上でプログラム選びの決め手になったのは、研修期間のほぼ全てを埼玉県内で過ごせることでした。4年間のプログラムのうち一時期だけ栃木県の本院に行く必要があるものの、あとはずっと埼玉なので引っ越ししなくて済むのがいいなと思いました。僕の場合は専攻医2年目と3年目に済生会加須病院と越谷誠和病院を1年ずつ回り、最終年となる来年のどこかで本院へ勉強に行く予定です。こちらのプログラムは専攻医の募集定員がそれほど多くないので、症例の奪い合いになることもなく、軽症から重症例まで幅広く経験できています。

運動器疾患や外傷を中心に学び、専門医取得を目指す
埼玉医療センターにいた頃は月に4回ほど当直が回ってきました。入院患者さんは多い時で30人ほど担当しますが、チーム制なので休みが取りにくいということはありません。埼玉医療センターは3次救急医療機関なので、多発外傷や高エネルギー外傷などを診ることもありました。開放骨折や手指切断などで運ばれてくる患者さんも多く、最初は戸惑うこともありましたが、一つ一つの症例に向き合う中で医師として成長できたように感じます。また埼玉医療センターには足・手をはじめとした各分野の専門家がそろっているので、貴重な症例を経験できることも特徴の一つです。僕もしっかり勉強して専門医を取り、運動器疾患から外傷までしっかり診られる整形外科医になりたいと思っています。

 1日のスケジュール
1日のスケジュール
07:15
出勤
朝カンファがあるときは7時前に出勤
07:30
-8:00 情報収集
カルテでバイタルや検査結果など確認
08:00
-9:00 回診
09:00
-14:00 手術、救急車対応など
14:00
-17:00 手術、外来、救急車対応など
外来日は週2日
17:30
-18:00 退勤
緊急手術あると遅くなることあり
 経験症例
経験症例

産婦人科
産婦人科プログラム
産婦人科
産婦人科プログラム
産婦人科
産婦人科プログラム
何でも聞きやすい風通しのよい環境に恵まれ、産婦人科領域を網羅的に経験
学生時代の実習でお産に立ち会い、産婦人科に進むことを決意したという能重先生。将来ママになったとしても「今の職場で仕事を続けたい」と話す能重先生に、プログラム選びのポイントや働きやすい職場環境について伺います。
取材日:2024年3月
更新日:2025年04月

能重 仁美のうじゅう ひとみ
医師期間
専攻医1年目 医師3年目※取材当時
出身大学
獨協医科大学
お住まい
住宅手当
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
先輩方が優しくて何でも聞きやすい。風通しのよさが一番の魅力
母が薬剤師ということもあり、子どもの頃から医療系に興味がありました。その中で医師を選んだのは、患者さんと向き合いながら治療ができる点にやりがいを感じたからです。そして大学の実習でお産を見たときの感動を忘れられず、自分の直感を信じて産婦人科に進むことを決めました。私は初期研修もこちらでお世話になったのですが、産婦人科は医局の雰囲気がとても良かったんです。上の先生方はみなさん優しい方ばかりですし、分からないことがあれば何でも質問しやすくて、丁寧に教えてくださいます。初期研修を通して、ここでなら安心して勉強できることが分かっていたので、専門研修プログラムを選ぶ際もほとんど迷うことはありませんでした。
3年間の専門研修プログラムで産科・婦人科領域を網羅的に経験
当センターは産科と婦人科が分かれているわけではないので、産婦人科領域の疾患を網羅的に経験することができます。ただし大学病院という特性上、がんをはじめとした婦人科疾患の比重が大きいように感じます。お産については緊急の帝王切開手術を担当したこともあるのですが、時期によってはお産が少なくなるなど症例数に若干の変動があります。とはいえ3年間のプログラムでは外の病院に行く機会もありますので、お産に関しては外勤先でしっかり経験を積めるかなと思います。私はいま専攻医1年目で、来年以降どの病院に行くのかまだ決まっていませんけれど。埼玉県や栃木県にある提携病院の中から研修先を見つけて、お産をたくさん経験してくる予定です。
ママ医師も多数在籍。チーム制で働きやすさは折り紙付き!
今は毎朝8時頃に出勤して、カンファレンスを終えた後に手術や病棟業務などを担当しています。日中の業務が終わると夕回診をして、遅くとも夜7時には病院を後にできるでしょうか。最近は「医師の働き方改革」が話題になっていますが、当センターの働きやすさは以前からずっと変わることはありません。チーム制のおかげでお休みが取りやすく、オンとオフをうまく切り替えながら仕事ができるのも、このプログラムを選んだ決め手でした。子育てに対する理解がある職場なので、ママさん医師もたくさん活躍されています。私もいずれ結婚して子どもに恵まれたとしても、ここでなら仕事と家庭を両立させながら仕事を続けられるような気がします。
 1日のスケジュール
1日のスケジュール
08:00
出勤
08:40
カンファレンス
09:00
手術/外来
17:00
回診
18:00
退勤
 経験症例
経験症例

麻酔科
獨協医科大学埼玉医療センター 麻酔科
麻酔科
獨協医科大学埼玉医療センター 麻酔科
麻酔科
獨協医科大学埼玉医療センター 麻酔科
麻酔科は「診断の連続」。オン・オフを切り替えて仕事もプライベートも充実
初期研修で麻酔科を回った際に「自分に合っている」と感じたという山口先生。大学院生として研究に従事しつつ専門研修プログラムに取り組む山口先生に、プログラム選びのポイントや現在の働きぶりなどを伺います。
取材日:2024年4月
更新日:2025年04月

山口 颯人やまぐち はやと
医師期間
専攻医2年目(医師4年目)※取材当時
出身大学
埼玉医科大学
お住まい
浅草
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
自分の手を動かし、頭で考える。麻酔科は「診断の連続」
学生の頃は「この科に進みたい」といったものはありませんでしたが、初期研修でいろいろ回ってみて麻酔科が自分に一番合っていると感じました。もともと手を動かすのが好きで、自分の頭で考えて解決策を見つけるのが好きだったというのが理由です。麻酔科の仕事は「診断の連続」のようなところがあり、その時々の状況に合せて判断したり対応したりすることが求められます。麻酔科ならば自分の強みがいかせるのではないかと思い、初期研修に引き続き専門研修プログラムに進みました。当センターは建物自体がキレイなのはもちろん、医局の雰囲気がとてもいいんです。上級医の先生方もみなさんとても面倒見がよくて、研究のチャンスもたくさんあります。初期研修の2年間でこうしたことを知っていましたので、プログラム選びで迷うことはありませんでした。

将来的には海外留学も。サブスペ取得も目指せる専門研修プログラム
4年間のプログラムでは3カ月だけ連携施設に行きますが、そのほかは基本的に当センターで勤務します。研修先は日光の医療センターや北海道大学、埼玉県立小児医療センターなどがあり、専門医取得した後、希望すれば海外留学に行かせてもらえるようです。とはいえ、足りない症例を集めるために外へ行く必要はなくて、専門医に必要な症例はすべて当センターで経験できます。心臓麻酔、産科麻酔、小児麻酔などを幅広く学べる点は、当センターならでの強みではないでしょうか。これらのサブスペ領域には「強化月間」も設けられていて、ペインクリニックや気道管理をはじめとした各分野のエキスパートのもとで1カ月~3カ月間しっかりと学ぶことができます。僕も苦手分野をつくらないように幅広く経験を積み、神経ブロックなどもできるようになりたいと思っています。

オン・オフをしっかり切り替え、仕事もプライベートも充実
毎朝8時からカンファレンスがあるので、それに間に合うように7時半頃までには出勤しています。カンファレンスが終わると順次麻酔業務に入り、大きな手術の場合は1日1件、短時間の手術であれば1日に4件ほど担当することがあるでしょうか。初めて心臓麻酔を担当した時には戸惑いもありましたが、2回目、3回目と経験を積むにしたがってスムーズに進行できるようになり、自分の仕事に自信が持てるようになりました。日中の業務が終わると夕方5時頃には解散となることが多くて、プライベートな時間をしっかり確保できています。当直は月に3回ありますが、事前に希望を伝えておけば都合の悪い日を避けていただけるのでありがたいです。何かと趣味が多い自分としては、仕事と趣味を両立できる今の環境にまったく不満はありません(笑)。

 1日のスケジュール
1日のスケジュール
07:30
出勤
その日の準備の程度に応じて自分で出勤時間を調整
08:00
カンファレンス
08:30
患者入室、麻酔導入
12:00
昼休憩
17:00
退勤
精神科
獨協医科大学埼玉医療センター精神科専門研修プログラム
精神科
獨協医科大学埼玉医療センター精神科専門研修プログラム
精神科
獨協医科大学埼玉医療センター精神科専門研修プログラム
泌尿器科から精神科へ。残業なし&当直なしの恵まれた環境で専門医取得を目指す
泌尿器科医として勤務した2年間を経て、精神科の専門研修プログラムに取り組む吉田先生。泌尿器科から精神科への転科を決めた理由は何だったのでしょうか? プログラム選びのポイントや将来のビジョンなどを含めて伺います。
取材日:2024年4月
更新日:2025年04月
吉田 友莉子よしだ ゆりこ
医師期間
専攻医3年目/医師7年目※取材当時
出身大学
東京女子医科大学
お住まい
病院から電車で20分程度の賃貸
将来の目標
専門医、指定医、指導医、司法精神の勉強をすること
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
「児童に関わる疾患」を診るため、泌尿器科から精神科へ
小児泌尿器科を勉強する中で発達障害についてさらに勉強したいと考え、思い切って精神科に転科して専門医を取ることにしました。当センターの「こころの診療科」は、患者さんの大半が未成年者です。発達障害や不登校を中心に多彩な症例を経験できること、指導体制が充実していることなどが決め手になり、こちらでお世話になることを決めました。実際に診療してみて、何か困ったことがあれば毎朝のカンファレンスですぐに相談できるので助かっています。私は泌尿器科から転科しましたが、ほかにも「転科組」の医師が何人かいますし、全体的に風通しのよさを感じます。医局の雰囲気がとてもよいので、こちらを選んで間違いなかったと思っています。
不登校の子が高校へ。うれしい変化にやりがいを感じる日々
外来では多い時で20人前後の患者さんを担当しています。発達障害や気分の落ち込みなどは年齢を問わず診ていますが、不登校のお子さんにうれしい変化がみられたりするとやりがいを感じますね。たとえば中学で不登校になった子に対し何度も診察を重ねた結果、『卒業式に出ないと後悔する』と言ってくれた上に高校にも通うことができるようになったケースがあり、とてもうれしかったです。あいにく当センターには精神科病棟がないため、足りない部分は連携施設で勉強することになるのですが…、私としては子どもの精神科症例をたくさん学べることにメリットを感じています。まずは専門医、次に指定医と指導医を取って、司法精神鑑定のほうに進むのもいいかなと考えています。
残業なし&当直なし。ワークライフバランスは抜群!
精神科に転科して、自分がやりたかったことができているので毎日が充実しています。当センターの「こころの診療科」はほぼ毎日定時に帰れて、当直がないところも恵まれているなと思います。月に4回ほどオンコールが回ってきますが、呼び出されることはほぼありません。有休もとりやすく、ワークライフバランスはバッチリではないでしょうか(笑)。男性医師が育休を取ったという事例もあるようですし、産休・育休は問題なく取れると思います。年次が上がるのにしたがって業務量が増えることもなく、専攻医だからといって雑用ばかりということもなく、指導体制もしっかりしています。これまでの経歴が問われることもありませんので、今の診療科が「しっくり来ないな」と感じている人にもおすすめできるかなと思います。
 1日のスケジュール
1日のスケジュール
08:30
出勤/カンファレンス
毎日朝カンファをして新患症例や悩んでいるケースなどについて相談できる
09:00
外来(週3日)
救命救急センター出向時は週2日、出向時は週1日
12:30
昼食
外来が一段落ついたら
14:00
病棟依頼の診察
せん妄や不眠などについて依頼が来るため対応
15:00
レポートや書類作成
16:00
毎週火曜日に勉強会(持ち回り)
17:00
退勤
 経験症例
経験症例

小児科
獨協医科大学埼玉医療センター 小児科専門医養成プログラム
小児科
獨協医科大学埼玉医療センター 小児科専門医養成プログラム
小児科
獨協医科大学埼玉医療センター 小児科専門医養成プログラム
大学病院・小児専門病院で多彩な症例を経験し、小児医療のスペシャリストに
小児科医の父の背中を追うようにして医師になったという佐々木先生。初期研修でさまざまな診療科を経験する中でも「小児科に一番やりがいを感じた」と話す佐々木先生に、現在取り組んでいるプログラムの特徴や魅力を伺います。
取材日:2024年3月
更新日:2025年04月

佐々木 侑ささき すすむ
幅広い疾患を深く学ぶことができます
医師期間
専攻医3年目(医師5年目)※取材当時
出身大学
お住まい
電車で片道20分で通勤
将来の目標
小児神経とてんかんを専門分野に勉強し、より包括的な医療を実施できる医者になること
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
小児科医のやりがいは、子どもたちの将来まで診られること
小児科は単に病気を治すだけではなく、子どもたちの将来まで見据えて一人一人に適した診療を行うことが大事になります。自分としてはそういったところが小児科ならではの魅力だと思いますし、初期研修でいろいろな科を回ってみてもやはり、小児科で診療している時が一番やりがいを感じました。また、小さな頃から小児科医の父の背中を見ながら育ちましたので、尊敬する父と同じ小児科を選んだ…というのも一つの理由になるかもしれません。今はまず小児科専門医を取ることを目標にしていますが、将来的にはサブスペに小児神経を考えていて、子どもたちの成長とともに経過を見ていく必要のある「てんかん」を診られるようになりたいと思っています。
複数の大学や小児専門病院を組み合わせて多彩な症例を経験
こちらのプログラムを選んだのは、当センターをメインにしつつ、提携先の医療機関でさまざまな症例を経験できる点に魅力を感じたからです。僕の場合は専攻医2年目に順天堂大学と埼玉県小児医療センターを回りましたが、希望すればこのほかに栃木県にある本院や東京都立小児総合医療センターでも勉強できます。1つの医療機関だけではどうしても症例に偏りが出てくる可能性がありますが、ほかの大学や小児専門病院で経験を積むことにより、軽症から重症例まで幅広く経験できると思います。当センターにはかぜなどで入院するお子さんも少なくありませんが、自分の治療によって患者さんが元気になり、笑顔で退院していく様子を見られた時は何とも言えないやりがいを感じます。
アットホームな雰囲気の中で、メリハリのある働き方が可能
当センターは大学病院でありながら堅苦しくないと言いますか、アットホームな雰囲気があってとても働きやすいです。専攻医の僕も一定の裁量を持ち、自覚と責任を持って診療することができています。たとえば以前、難病に指定されている脊髄性筋委縮症(SMA)の患者さんを担当した時などは、薬の選択や治療計画の立案などを任せていただきました。製薬会社の担当者と一緒に治療薬を検討し、SMAの専門家といえる医師にオンラインでアドバイスをいただき、診断から治療まで一貫して携われたことは大きな自信になりました。とはいえ忙しくて仕方ないかといえば決してそうではなくて、毎日午後6時頃には業務終了となり、当直明けも必ず帰れます。メリハリのある働き方ができるのも当センターのいいところかなと思います。
 1日のスケジュール
1日のスケジュール
08:00
出勤
08:30
カンファレンス・回診
09:00
手術・外来
12:00
昼食
17:00
カンファレンス
18:00
~19:00 退勤
 経験症例
経験症例

放射線科
獨協医科大学埼玉医療センター 放射線科
放射線科
獨協医科大学埼玉医療センター 放射線科
放射線科
獨協医科大学埼玉医療センター 放射線科
全身の疾患を画像で診る、放射線科医にやりがい
初期研修は、学生時代から興味があった放射線科で研修ができる病院を探し、獨協医科大学埼玉医療センターを選んだという田部井先生。後期研修も引き続き同院を選んだ理由や、プログラムの魅力などを伺いました。
取材日:2024年2月
更新日:2025年04月

田部井 杏菜たべい あんな
医師期間
出身大学
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
研修内容の幅広さと充実の指導体制、医局の自由な雰囲気が魅力
学生の頃から全身の疾患を画像として診ることができる放射線科に興味がありました。初期研修中に当院の放射線科で約4カ月間研修し、指導医の先生やレジデントの先生方が熱心に教育してくださったので、専門研修プログラムも迷わずこちらを選びました。私と同じ選択をした同期が複数いたことも心強かったです。研修内容の幅広さ、自由度の高さに加えて、先生方が非常に優しく、医局の雰囲気がとても良いのも決め手になりました。雰囲気の良さは毎日働く上でとても大切ですから。当科の魅力は自分自身で勉強したいことを追求しながら、わからない点や心配なことは、どんな些細なことでも上の先生に丁寧に教えていただけることです。勉強熱心な同期たちと、何でも気軽に相談し合える環境が気に入っています。

専攻医1年目はIVR、画像診断など3カ月単位で幅広い領域を経験
当院の専門研修プログラムは2023年にできたばかりで、私たちが初代です。前例がないので、手探りになることもありますが、教授を中心に専攻医の希望を汲みながら、3カ月単位でスケジュールを組んでいただいています。私の場合は専攻医1年目にIVR、画像診断、超音波検査、放射線治療と、幅広い領域を経験することができました。放射線治療では、子宮頸がんの骨盤内転移により、右下肢に強い痺れと疼痛がある入院患者さんに緩和照射を2回行ったところ、嘘にように痛みが取れたと聞き、とても嬉しかったです。同時に、放射線の高い治療効果を改めて実感しました。出向のタイミングについては教授と相談しながら、柔軟に対応していただけます。私は24年4月から東京都立大塚病院へ半年間の出向が決まりました。

指導医にも恵まれ、学びもプライベートも充実した日々
ワークライフバランスは非常に取りやすい環境で、家族や友人と数回旅行にも出かけました。上の先生方は在宅で読影をされることも多く、子育てとの両立もしやすいように思います。体調不良など急な休みも取りやすく、基本的に当直はありません。週1回外勤をいただく分、月1~2回土曜日出勤がありますが、レジデントが主となるため、平日とは違う学びがあります。緊急の読影依頼でも、指導医の先生方に在宅でレポートを確認・修正していただけるので、安心して対応できています。こうしたサポートのおかげで、依頼科の先生方から感謝の言葉をいただくことも多くあります。指導医に恵まれ、専攻医1年目は非常に充実した研修が受けられています。今後の目標は、まずは全身の画像診断を一通りマスターすることですが、研修を通じて特に興味を持った分野をさらに深く学びたいと思っています。

 1日のスケジュール
1日のスケジュール
08:45
出勤
09:00
読影
12:00
昼休憩
13:00
読影
18:00
退勤
リハビリ科
獨協医科大学埼玉医療センター リハビリテーション科
リハビリ科
獨協医科大学埼玉医療センター リハビリテーション科
リハビリ科
獨協医科大学埼玉医療センター リハビリテーション科
急性期から慢性期まで、患者さんの生活に寄り添う治療を
初期研修で回ったリハビリテーション科に興味を持ち、現在は獨協医科大学埼玉医療センターで専門研修プログラムに取り組んでいる椙田(すぎた)先生。研修先選びで重視したことや、リハビリテーション科医の魅力などを伺いました。
取材日:2024年2月
更新日:2025年04月
椙田 麻奈すぎた まな
医師期間
出身大学
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
リハビリテーション科医の、患者を取り巻く環境を診る視点に感動
初期研修で、退院後の患者さんに必要な福祉サービスやサポートを見極めるために行う「家屋調査」に同行しました。その際、他科が急性期の“病気”に焦点を当てているのに対し、リハビリテーション科は“病気の後の生活”まで診るという点に大きな魅力を感じました。急性期から回復期、そして自宅に戻られてからも、患者さんの生活に長く・深く関わっていくリハビリテーション科は、非常にやりがいのある科です。この分野を専門にすると決め、まずは東京医科歯科大学病院のリハビリテーション科に所属しました。現在も同科に所属しながら、専攻医1年目の後半は、同大の部長の助言もあって、こちらの病院でお世話になっています。医科歯科のプログラムのローテーション先は整形外科系統の病院が多いのですが、こちらは私が興味のある脳血管障害の症例を多く経験できることが決め手になりました。
脳血管疾患を中心に、呼吸器・循環器、小児まで幅広い症例を経験
現在は1日平均2~10人程度の患者さんを担当し、中でも脳血管疾患の患者さんを多く診させていただいています。他にも、呼吸器や循環器の疾患、がん、小児の脳性麻痺、心臓リハビリなど、幅広い経験ができるのは大学病院ならではです。整形外科出身の医科歯科の指導医と、脳血管障害がご専門の当院の指導医では同じリハビリでも着目する視点が異なります。専門分野の異なる複数の指導医から学ぶことで、より多方面の知識を身に付けることができそうです。脳卒中等の後遺症で、自分の力では歩けなくなってしまった患者さんが、適切なリハビリ装具を使用することで再び歩けるようになった時は、とても感動しました、リハビリには患者さんの人生や生活を変えるほど大きな効果があることを実感しています。
障害が残っても、在宅・社会復帰を支えられる医師を目指す
専攻医2年目は回復期病院で初めて主治医を担当します。今より忙しくなりますが、当科は基本的に当直もオンコールもないので、ワークライフバランスは取りやすいと思います。リハビリテーション科は新しい領域なので、指導体制が整っている大学病院で研修を受ける方が、多くの学びが得られるのではないでしょうか。プログラムごとに特徴があるため、自分の合ったプログラムを選ぶことをおすすめします。近年は、30代でくも膜下出血を発症する患者さんもおり、今まで普通にできたことが突然できなくなるストレスから、リハビリに後ろ向きになりがちな方も少なくありません。そんな患者さんの精神的な支えとなり、治療意欲をどう引き出すかも、医師や療法士の腕の見せ所です。将来は、たとえ障害が残っても、患者さんが前向きに生きられる手助けができる医師を目指したいと思います。
 1日のスケジュール
1日のスケジュール
08:20
未定
他科からのリハビリ依頼にざっと目を通す
08:50
朝礼
リハビリテーション科全科の朝礼 部長・技師長等から周知事項など、特にコロナやインフルエンザの流行時期は、感染対策が必要なゾーンなど情報共有。
08:55
入院患者コンサルトの割り振り
他科からのリハビリ依頼(コンサルト)をリハ医で分担。特に勉強になる症例を部長がピックアップし、レジデントに割り振られることが多い。
09:00
~12:00 入院患者のリハ前診察 外来リハ前診察
呼吸器、循環器、整形外科的な問題がないかなど、特に注意して診察。リハを実施することの有益性がリスクを上回るかを見極め。PT、OT、STの中から必要なリハを処方し、療法士へ依頼。
13:00
~17:00 装具診(火)、嚥下内視鏡検査・嚥下造撮(水)、その他、入院患者のリハ前診察 外来リハ前診察
装具診では、リハ医が装具の適応や使用状況などを問診、診察。その後、義肢装具士が採寸・採型、PTが歩容を確認し適宜アドバイス。
17:00
~18:00 退勤

救急科
獨協医科大学埼玉医療センター 救急科専門医養成プログラム
救急科
獨協医科大学埼玉医療センター 救急科専門医養成プログラム
救急科
獨協医科大学埼玉医療センター 救急科専門医養成プログラム
手厚いサポート体制の下、救急医に必要な症例を多数経験
命の危険に瀕した重症患者の治療に当たる三次救急の世界に興味を抱き、救急医療科の専門研修プログラムに取り組んでいる伊東先生。獨協医科大学埼玉医療センターを研修先に選んだ理由や、救急医療のやりがいなどをお聞きしました。
更新日:2024年10月

伊東 雅記いとう まさき
医師期間
専攻医1年目(医師3年目)※取材当時
出身大学
東海大学
お住まい
病院から徒歩10分の賃貸
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
専攻医1年目から、救急ホットラインのリーダーに
僕は初期研修もこちらでお世話になったのですが、ローテーションで救急医療科を回った時に、重症の患者さんが元気になって退院される姿を見て、救急医療に興味を持ちました。 また、点滴から栄養、リハビリまで包括的に管理・ケアする集中治療管理についても深く学びたくて、救急医療科に進むことを決めました。 当院は重篤な患者に対して高度な救命救急医療を提供する三次救急医療機関です。 1日の受け入れ件数は少ないですが、他の医療機関では診察困難な救急患者を積極的に受け入れており、三次救急ならではの多彩な症例を経験できています。 上級医の見守りの下、1年目から現場の救急隊員らと、ホットラインと呼ばれる専用電話を通して重症患者の受け入れを円滑に行うリーダーを任せていただき、緊張感はありますが、救急医療科ならではのやりがいを感じています。

5人の専攻医一人ひとりに上級医が付くメンター制も魅力
獨協医科大学埼玉医療センターを研修先に選んだ決め手が、医局の雰囲気の良さでした。 私の代は同期が5人と、他の代より多いのですが、専攻医一人ひとりに上級医が付くメンター制を採用しており、迷った時は何でも相談できます。 瞬時の判断が必要な現場ですから、こうした手厚いサポート体制はやはり心強いです。 同期同士の関係性も良く、「できること」「できないこと」など研修の進捗状況を定期的に振り返りながら、切磋琢磨して成長できる環境は、とても恵まれていると感じます。 土日勤務はありますが、休日のオンコールはありません。 当直は月5~6回あるものの、医局員が多いのでシフトが組みやすく、オンオフの切り替えはしやすいと思います。 二次救急の症例は出向先の医療機関で学ぶことになりますが、埼玉県内の関連病院で受けられる点も、私にとってはメリットの一つです。

まずは救急科専門医を取得し、将来は内視鏡専門医にも挑戦
救急医療科は命を救えた喜びと同時に、救えなかった命と向き合い、悔しい想いをすることも多い職場です。 専攻医1年目の自分には何もできない経験をしたからこそ、この先同じ症例に出合った時は、自分でしっかり治療ができる医師になりたいです。 そのためにも、経験から学んだことを今後に生かして、成長していきたいと考えています。 まずは救急科の専門医取得を目指し、その後はサブスペシャルティとして、元々興味のあった消化器内視鏡専門医の取得に挑戦するつもりです。 実は、現在も週1回の外勤先で、内視鏡を学ばせていただいています。 そんな風に救急科専門医のスキルを基礎として、さらなるスペシャルティ領域を習得して活躍できる点も私には魅力でした。 何科を専門にするか迷っている人こそ、救急医を検討してみてほしいですし、当院には成長できる環境が整っています。

 1日のスケジュール
1日のスケジュール
07:40
出勤
08:00
カンファレンス
09:30
病棟回診
10:00
病棟業務、初療対応
16:00
病棟回診
16:40
退勤
入りの先生に申し送り

内科
獨協医科大学埼玉医療センター内科専門医プログラム プログラム責任者
内科
獨協医科大学埼玉医療センター内科専門医プログラム プログラム責任者
内科
獨協医科大学埼玉医療センター内科専門医プログラム プログラム責任者
6つの診療科が集結した研修プログラム。「医師の働き方改革」に配慮し、合理的・効率的な学びをサポート
学校の勉強では物理と数学が得意だったという田口先生は、大学5年生のときに循環器内科に進むことを決意したと言います。現在は循環器内科の診療部長であると同時に、内科専門医研修プログラムの責任者も務める田口先生に、獨協医科大学埼玉医療センターならではの魅力を伺いました。
取材日:2025年2月
更新日:2025年03月

プログラム責任者 田口 功たぐち いさお
ピラミッドは礎の石が多いほど高くなります。全ての領域において全力で勉強してください。当病院の内科専門プログラムでは、各内科診療科の垣根が低く、自分の診療科に所属しながら、全ての領域の症例が経験できる効率的なプログラムです。例えば、循環器内科に所属しながら、了承を得たうえで、血液内科の症例も経験できます。J-OSLER登録において、時間と労力が大きく節約できます。
医師期間
医師34年目 ※取材当時
出身大学
群馬大学医学部、H3年卒
経歴
1991 群馬大学医学部卒業 獨協医科大学第一内科
1994 足利赤十字病院循環器科
1997 獨協医科大学病院 心血管肺内科 集中治療部 救命救急センター助手
2008 獨協医科大学 心血管肺内科 准教授
2012 獨協医科大学病院 再生医療センター 副センター長兼任
2014 4.1.獨協医科大学越谷病院 循環器内科主任教授(現職)
認定
内科専門医、循環器専門医、心血管カテーテルインターベンション名誉専門医
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
内科専門医研修プログラムの責任者として若手医師の育成を担う
高校の頃から物理と数学が好きだった僕にとって、大学5年で出会った循環器内科学は学問としての楽しさがありました。物理数学的な基礎の解明や病態の理解に触れ、「自分が進む道は循環器内科しかない」と心に決めました。また街中で誰かが突然倒れて「お医者さんはいませんか?」となった場面でも、循環器を学んでいれば自信をもって「はい」と返事ができますからね(笑)。大学卒業後は獨協医科大の第一内科(循環器内科)に籍を置いて研鑽を積み、現在は循環器内科の診療部長(主任教授)を務めるほかに内科専門医研修プログラムの責任者として後進の育成にあたっています。また日本循環器学会の専門医試験の問題作成にも携わっており、さまざまな角度から専攻医の皆さんをサポートしています。

6つの診療科が集結した合理的・効率的な研修プログラム
当院の内科は埼玉県内において初診患者数がもっとも多いことが特徴であり、「当院で経験できない症例はない」と言っても過言ではありません。実際にプログラムに参加したほぼ全ての専攻医が3年間で内科専門医を取っており、循環器内科に所属する専攻医はその翌年に循環器専門医を取得しています。内科専門医の取得にはJ-OSLERへの症例登録が欠かせませんが、この点においても当院のプログラムは大きな強みがあります。糖尿病内分泌・血液内科/呼吸器・アレルギー内科/消化器内科/循環器内科/腎臓内科/脳神経内科の6つの診療科がプログラムに参加しているため、症例を獲得するために他の診療科をローテーションする必要はありません。たとえば循環器内科に所属する専攻医は上級医の承諾を得た上で、血液内科の患者さんの診療を経験してもらうことができます。ピラミッドは礎の石が多いほど高くなりますから、全ての領域において全力で勉強してほしいと思います。
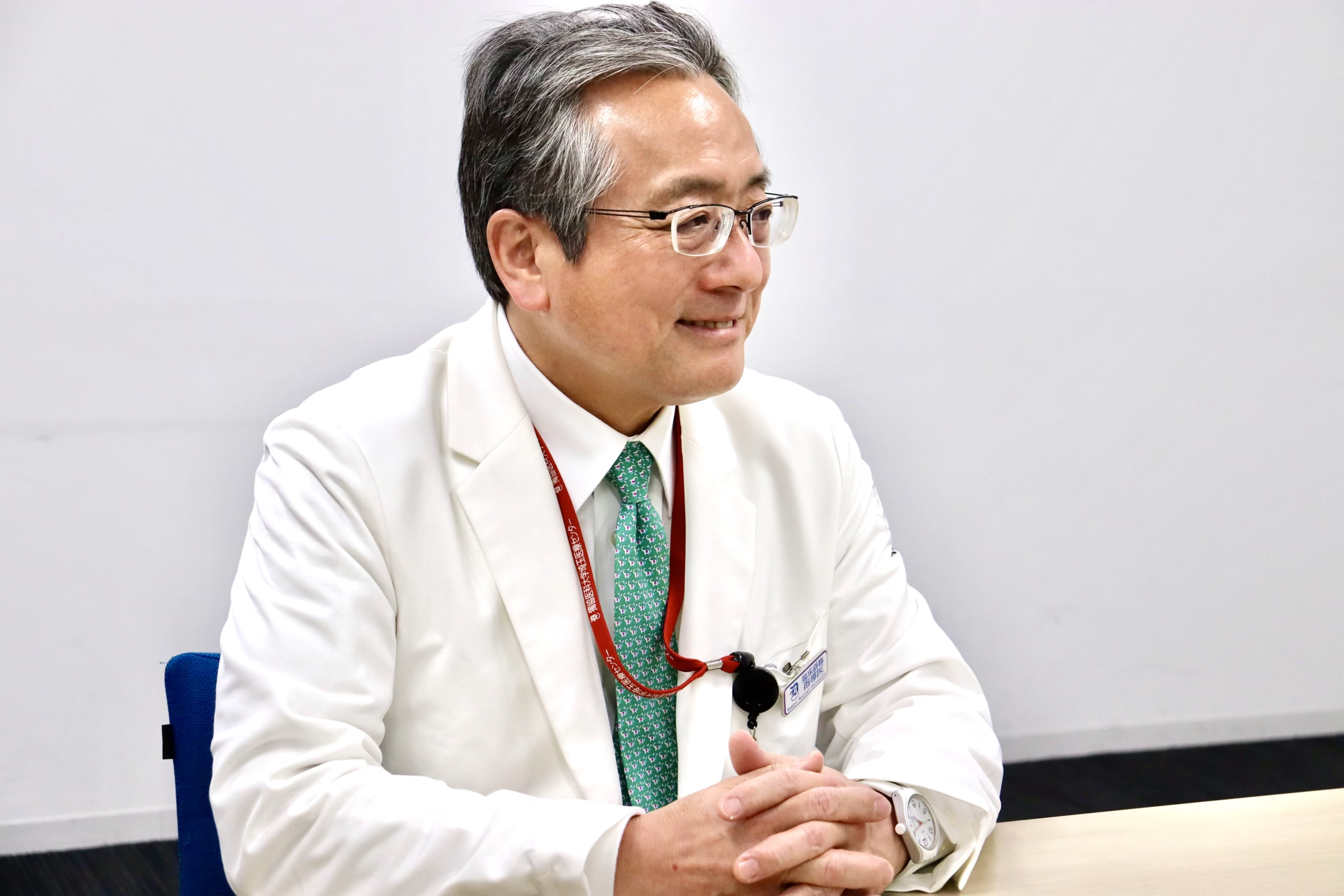
「医師の働き方改革」にも配慮して一人一人の学びをサポート
僕が率いる循環器内科では、医師5年目で内科専門医を取得、6年目で循環器専門医、8年か9年目でカテーテル、超音波、不整脈などサブスペ領域の専門医資格を取るのが一般的です。おおむね10年目頃までには論文を書いて博士号を取り、その後は外部の病院へトレーニングに行ったり、海外留学に行ってもらったりしています。僕も忙しい合間を縫って入院患者さんのカルテを全てチェックし、治療方針や処方薬などについて疑問があれば専攻医とコミュニケーションを取って情報共有したり、カンファレンスで症例検討を行ったりしています。最近は医師の働き方改革などによって時間外労働にも上限規制がありますから、早い時間からカンファレンスを始めたり、個別にカンファレンスを行ったりして勤務時間内に業務が終わるようにといった配慮もしています。
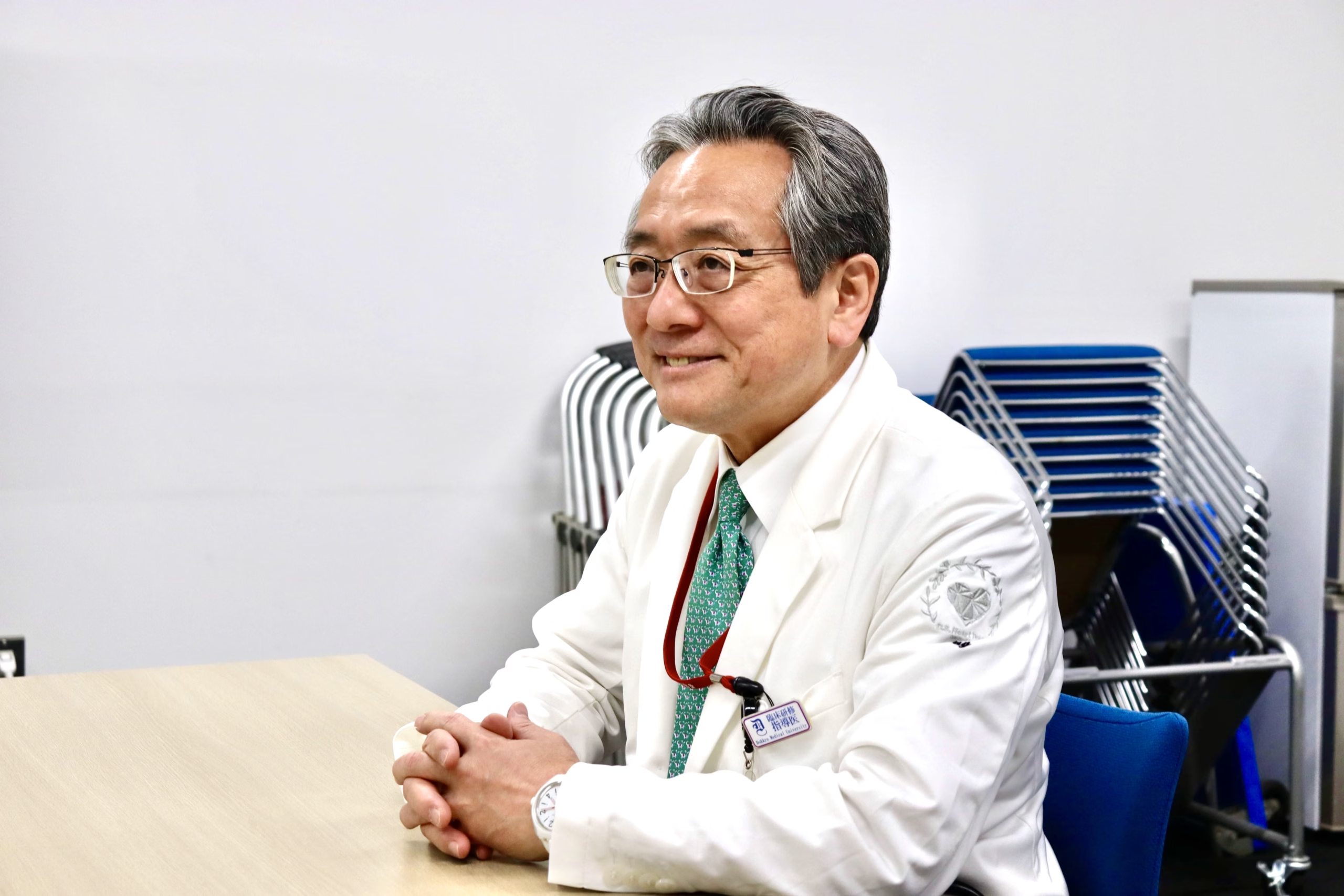
 1日のスケジュール
1日のスケジュール
08:30
出勤
6カ月ごとに各チームをローテーションし、左記の内容を習得する
初診外来、緊急対応
3年間で内科専門医取得、翌年に循環器専門医取得
心臓カテーテル検査・治療
3年間で冠動脈疾患、不整脈、心不全の検査・診断・治療計画ができるよう研鑽
不整脈カテーテルアブレーション・ペースメーカ
循環器専門医取得後、学位論文の準備
心エコー、心不全精査治療
核医学検査・負荷検査
心臓リハビリテーション
集中治療
17:10
退勤
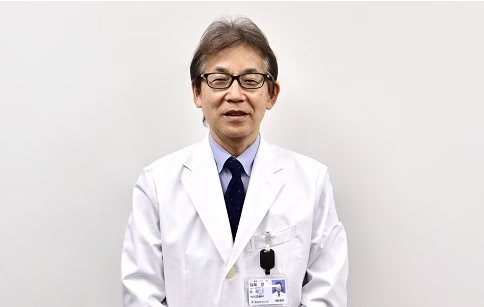
総合診療科
獨協医科大学埼玉医療センター総合診療専門医研修プログラム プログラム責任者
総合診療科
獨協医科大学埼玉医療センター総合診療専門医研修プログラム プログラム責任者
総合診療科
獨協医科大学埼玉医療センター総合診療専門医研修プログラム プログラム責任者
専攻医×大学院生の二刀流もOK。病院での診療と在宅医療を通して総合診療医としての成長をサポート
外科医としてキャリアをスタートした齋藤先生は、総合診療科の立ち上げに参加したことをきっかけに、この領域を専門に経験を重ねてこられました。現在は総合診療科主任教授として臨床と教育の両面に力を尽くす齋藤先生に、獨協医科大学埼玉医療センターならではの魅力を伺いました。
取材日:2025年2月
更新日:2025年03月
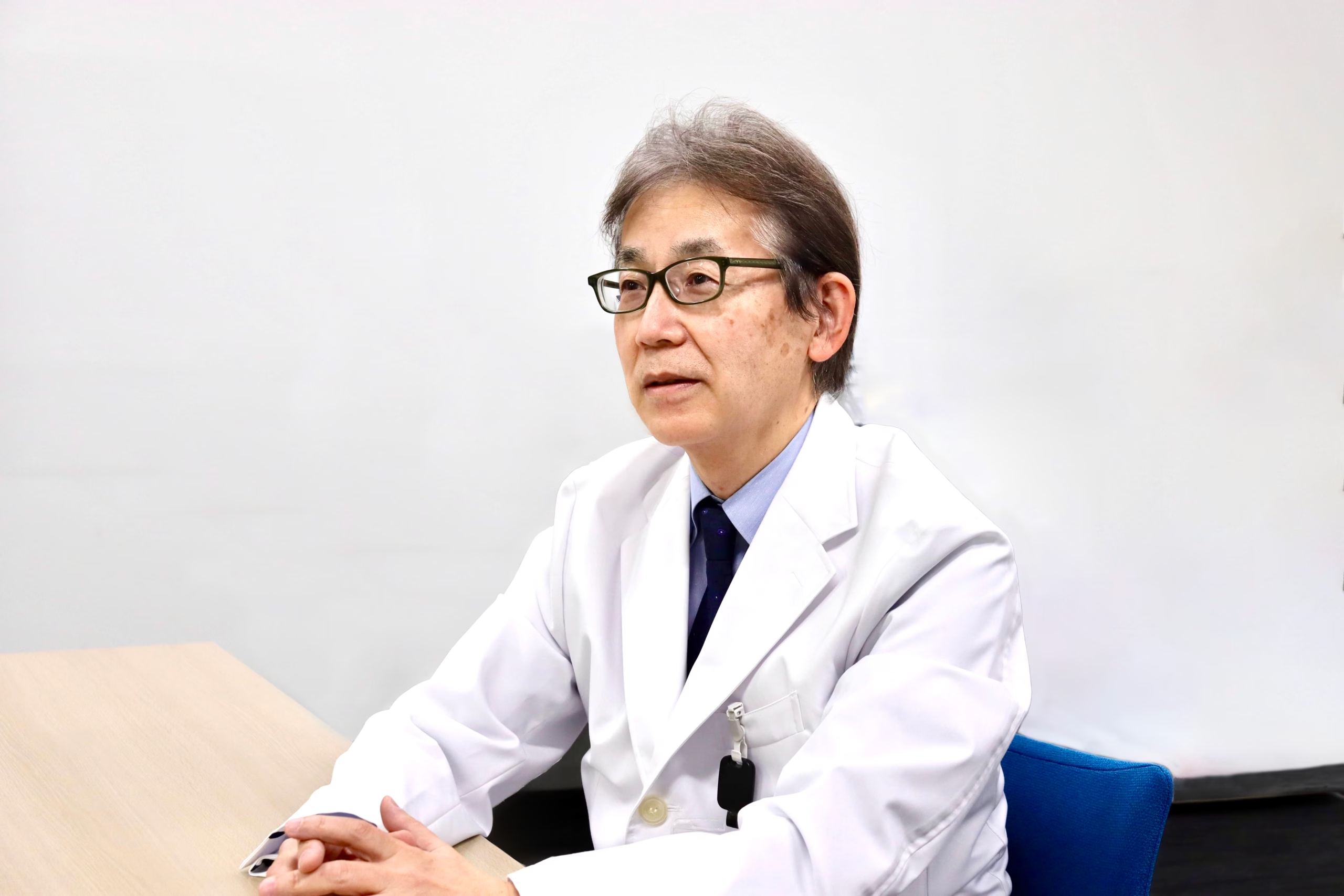
プログラム責任者 齋藤 登さいとう のぼる
総合診療科は症状がありながらも、要因不明や複数の症状があって診療に至らない患者さんなどを、地域の医療機関や院内他科を通して紹介いただいています。 “患者さんや紹介医に対する丁寧な医療”を心がけ、東洋医学と西洋医学を駆使し、病名が特定されなくても、苦しんでいる患者さんの症状を和らげることに努めています。特に総合診療医には個人~家族~社会に対して多様な医療サービスを包括的かつ柔軟に提供する役割が期待されています。その取り組みの一環として、大学病院では珍しい訪問診療を行う在宅医療部門を兼務担当しています。この部門では、地域の医療機関に移行し難い事例を院内の各科から在宅医療部門へ依頼を受け、訪問診療を行うことで、患者さんが住み慣れた地域で安心して生活できるよう機動性を発揮して活動しています。 ”常に全身を診る””幅広く学んで、全体的な視野を持つ”ことをモットーに、診療に役立つスキル修得に向けた指導(腹部・心臓・体表エコーや消化管内視鏡、漢方診療のアドバイスなど)を行っています。①内科/外科・救急を超えた幅広い視点、②病院診療~在宅医療の研鑽、③西洋医学~漢方医学の実践が特色です。
医師期間
医師39年目 ※取材当時
出身大学
東邦大学医学部/1986年卒、東京女子医科大学大学院/1990年卒
経歴
1986(昭和61)年東邦大学医学部を卒業後、1990(平成2)年、東京女子医科大学大学院博士課程(外科学専攻)修了、学位取得。
同大学第二外科でキャリアスタートの後、総合診療科設立に携わり講師・准教授として活動。クリニカルパス推進室長も務めチーム医療推進に貢献。
2016年、獨協医科大学医学部教授に就任。
2019年より獨協医科大学埼玉医療センター総合診療科主任教授として臨床・教育の両面で尽力している。
認定
日本病院総合診療医学会認定病院 総合診療医・指導医、日本プライマリ・ケア連合学会 プライマリ・ケア認定医・指導医、日本救急医学会 専門医、日本外科学会 認定登録医、日本消化器内視鏡学会 専門医・指導医、日本消化器病学会 専門医・指導医 など
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
東洋医学と西洋医学を駆使して、苦しんでいる患者さんの症状を和らげる
僕が東邦大学医学部を卒業した頃は今のようなローテーションもなく、総合診療という言葉もあまり知られていませんでした。そんな僕が総合診療に携わるようになったのは東京女子医大の第二外科にいた頃、一人の患者さんの全身を診られるような診療部門が必要だろうという話が持ち上がり、創設メンバーとして参加したのが始まりでした。このときのプロセスが評価されて当院に総合診療科を設立する際に声がかかり、2016年に獨協医科大学医学部教授に就任、2019年に総合診療科主任教授となりました。総合診療科では、何らかの症状がありながらも原因の特定に至らなかったり、複数の症状があるために適切な治療に結びついていなかったりする患者さんを広く受け入れ、東洋医学と西洋医学を駆使して診療にあたります。「患者さんや紹介医に対する丁寧な医療」を心がけ、たとえ病名が特定されない場合でも、苦しんでいる患者さんの症状を和らげるために力を尽くしています。

総合診療医ならではの知見を生かして、「訪問診療」にも注力
一口に総合診療と言っても、最近は救急に近いことをやっていたり、病気を診断することに特化したり、病院ごとに特色ある診療が行われています。その中で当院の特徴は、総合診療科として訪問診療を行っていることが挙げられます。当院には大学病院としては珍しい在宅医療部門があり、総合診療科の医師が訪問診療を担うことにより、患者さんご本人やご家族、地域社会に向けて多様な医療サービスを包括的かつ柔軟に提供できるよう努めています。在宅医療部門では地域の医療機関への移行が難しい患者さんを担当し、患者さんが住み慣れた地域で安心して生活できるようにサポートします。患者さんの生活環境や心理面に配慮し、総合的な観点から診療を行うことによって得られた知識や経験は、地域の中で診療していく上でも大いに役立つことと思います。
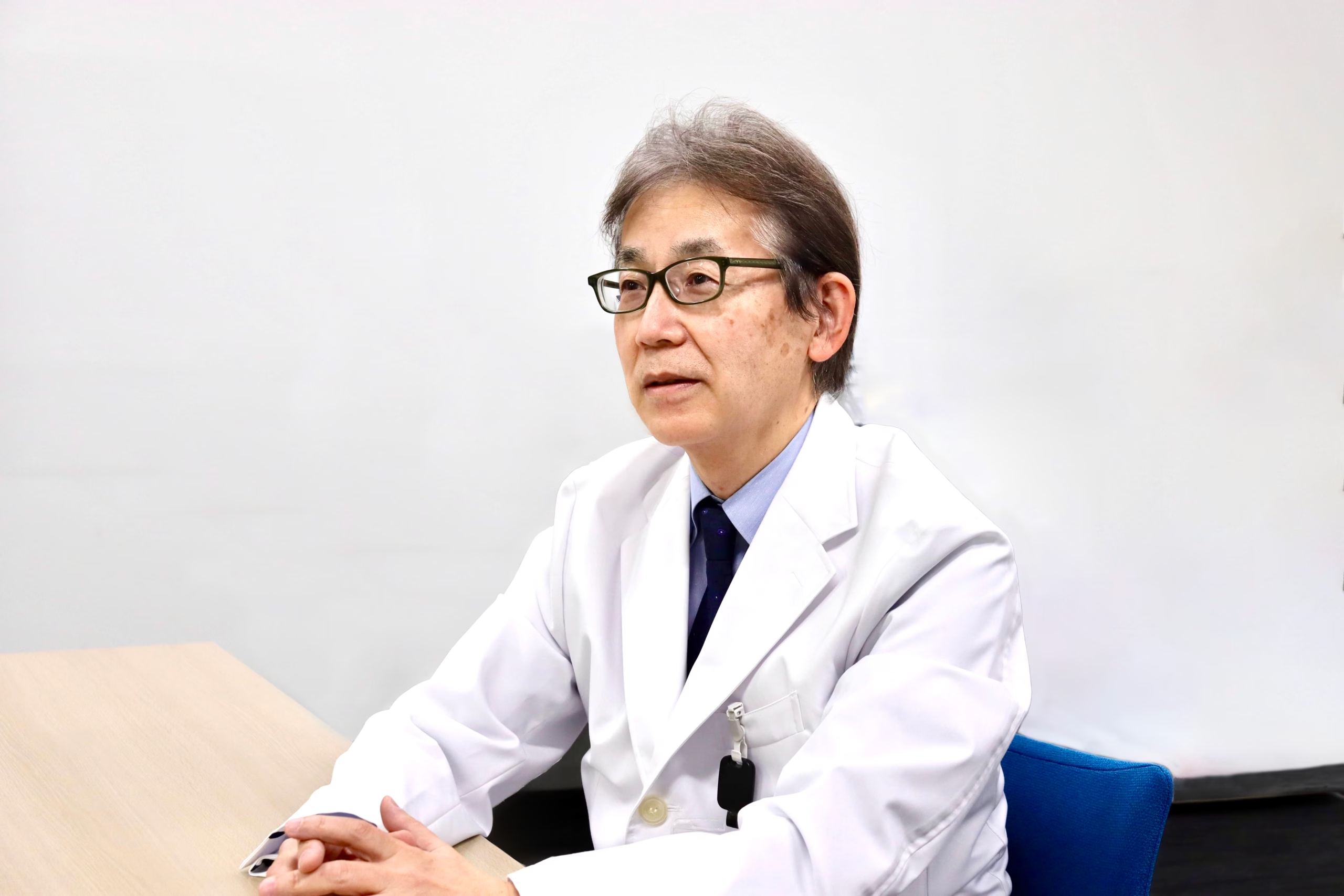
専攻医×大学院生の二刀流もOK。診療科の枠を超え「全身を診る」スキルを習得
3年間のプログラムにおいては「常に全身を診る」「幅広く学んで、全体的な視野を持つ」ことをモットーに、診療に役立つスキル習得に向けた指導を行っています。具体的には腹部・心臓・体表エコーや消化管内視鏡、漢方診療のアドバイスなどが挙げられ、内科/外科/救急の枠を超えた幅広い視点を持ち、西洋医学と東洋医学を融合した診療を実践できる医師の育成を目指します。院内での診療に加えて在宅医療を経験できることは当院ならではの特徴であり、総合診療科医学を専攻分野として「専攻医と大学院生の二刀流」が可能なこともメリットと言えるでしょう。初期研修を終えてそのままプログラムに取り組んでいただくのはもちろん、何らかの専門性を身につけた上でジェネラルな診療を経験してみたいという人、いずれは実家の医院を継承することが決まっている人などにも、ぜひ門を叩いてほしいと思います。
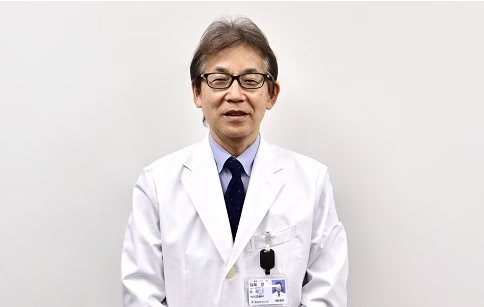
 1日のスケジュール
1日のスケジュール
08:30
出勤
09:00
外来診療
12:30
~13:30 昼休憩
担当症例にて時間は前後する
14:00
病棟往診・訪問診療(予定ある際に)
病棟往診は他科からの診療依頼ある際に上級医やチームメンバー揃って
15:00
症例カンファレンス・医局会(月曜)
さまざまな医療機関や診療科から紹介された症例を共有して自分の医療へ活かせる
16:30
多職種向け勉強会に参加
総合診療科と企業の共催:1~2回/月
17:00
~退勤
外来部門のみであり、夜間や休日の勤務はないため多様なライフスタイルと両立可能

泌尿器科
獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科専門医研修プログラム 指導医
泌尿器科
獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科専門医研修プログラム 指導医
泌尿器科
獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科専門医研修プログラム 指導医
医師のキャリア形成で重要なのは「後期研修への取り組み方」。指導医として最大限の支援を惜しまない
北海道大学卒業後、東京女子医科大学の泌尿器科に入局してキャリアをスタートさせた瀬戸口先生。泌尿器科を選んだ理由は、腎移植への興味だったと言います。現在は日本泌尿器科学会専門医・指導医として後進の指導にあたる瀬戸口先生に、獨協医科大学埼玉医療センターならではの魅力を伺いました。
取材日:2025年2月
更新日:2025年03月

指導医 瀬戸口 誠せとぐち きよし
今後のキャリア形成で最も大切なのは後期研修が始まってからの取り組む姿勢だと私は思います。今振り返ってみても医師のキャリアは終わりのない階段のようなものです。皆さんが登っていく階段を年間数段ずつ進む手伝いを、私たち指導医は最大限支援したいと考えています。
医師期間
医師28年目 ※取材当時
出身大学
北海道大学/平成9年卒
経歴
平成9年4月 東京女子医大学泌尿器科入局
平成20年4月 米国クリーブランドクリニック リサーチフェロー
平成23年4月 戸田中央総合病院 泌尿器科
平成25年5月 済生会栗橋病院 泌尿器科
平成27年10月 東京女子医科大学八千代医療センター 泌尿器科 助教
平成29年10月 獨協医科大学埼玉医療センター 泌尿器科 講師 現在に至る
認定
日本泌尿器科学会専門医・指導医、日本透析学会認定医・指導医
日本移植学会移植専門医、臨床腎移植学会専門医
日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会腹腔鏡技術認定医
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
腎移植への興味から泌尿器科へ。外来医長として後進の指導にあたる
私は北海道大学医学部出身で、大学の部活は野球をやっていました。泌尿器科に進んだ背景にも部活の先輩の影響があり、腎移植への興味と相まって泌尿器科を専門にしようと決めました。大学卒業後は東京に戻って東京女子医大の泌尿器科に籍を置き、アメリカ留学に行ったり、関連病院で診療したりしながら経験を積みました。私たちの頃は後期研修プログラムなどない時代でしたが、若手医師を指導する立場になった今言えるのは「後期研修に取り組む姿勢がその後の医師人生を左右する」ということです。医師のキャリア形成において後期研修の4年間がいかに大切かということを、プログラムに参加する専攻医に伝えられたらいいなと思っています。

医師のキャリア形成においては「後期研修への取り組み方」が重要
4年間のプログラムでは研修連携施設での学びの時間もありますが、基幹病院は当院です。専攻医の皆さんには4年間の大半を当院で過ごしてもらうことになりますから、私たち指導医が担う役割は大きなものがあると考えています。最近は○○ハラスメントに厳しい目が光っていますから、先輩医師が高圧的な態度をとることはありません。しかし患者さんは実験台ではありませんから、一定の手技を身につけてからでないと診療を任せられないことも事実です。もちろん私たちも精一杯サポートしますが、分からないところは自分でも勉強してもらったり、シミュレーションを繰り返したりして準備をすることも大切なのだと理解してもらえたらうれしいです。

プログラムの主役は専攻医。指導医として最大限の支援を惜しまない
私は泌尿器の中でも腎移植、ロボット手術、腹腔鏡手術、シャントケアなどを専門にしていて、医師免許を取得してもう30年近くになります。振り返ると医師のキャリアとは「終わりのない階段」のようなものです。そして指導医となった今は、階段を上っていく専攻医の皆さんをサポートすることしかできないことを痛感する場面も少なくありません。階段を上るのはあくまでも専攻医の皆さんであり、1年間に階段を何段上れるかは、一人一人のやる気次第と言えるからです。私たち指導医は専門研修プログラムに真摯に取り組む皆さんに対して、最大限の支援を惜しみません。自ら主体的に学び、努力を続ける人にこそ、ぜひ仲間になってほしいと思います。

 1日のスケジュール
1日のスケジュール
08:00
出勤、病棟回診
08:30
手術もしくは外来
12:30
昼食
13:00
2件目の手術
18:00
病棟回診
19:00
退勤

耳鼻咽喉科
獨協医科大学埼玉医療センター耳鼻咽喉科専門医養成プログラム 指導医
耳鼻咽喉科
獨協医科大学埼玉医療センター耳鼻咽喉科専門医養成プログラム 指導医
耳鼻咽喉科
獨協医科大学埼玉医療センター耳鼻咽喉科専門医養成プログラム 指導医
豊富な症例と充実の指導体制が自慢。耳・鼻・頭頸部外科などサブスペ領域の専門医取得もサポート
コモンディジーズから専門分野まで幅広い診療をしたいという思いから耳鼻咽喉科に進んだという海邊先生。現在は「めまい外来」も担当する海邊先生に、獨協医科大学埼玉医療センターならではの魅力を伺いました。
取材日:2025年2月
更新日:2025年03月

指導医 海邊 昭子うみべ あきこ
医師期間
医師15年目 ※取材当時
出身大学
獨協医科大学 2010年卒
経歴
2010年 獨協医科大学医学部卒業、同年獨協医科大学越谷病院(現:埼玉医療センター)臨床研修医
2012年 耳鼻咽喉科入局
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
小児・成人を問わずあらゆる患者さんを診て、診断から治療まで一貫して携わる
開業医だった父が診療する様子を見ながら育ちましたので、子どもの頃から「医師=町医者」のようなイメージがありました。小児から成人まであらゆる患者さんを診て、かぜなどの日常的な病気から専門的な分野まで適切に診療ができる。そんな医師になりたいと思っていた私にとって、診断から治療まで一貫して携わり、入局後の選択肢が多彩な耳鼻科は理想的な診療科と言えました。初期研修先だった越谷病院(現・埼玉医療センター)の耳鼻科の雰囲気のよさにも惹かれ、そのままお世話になることを決めました。当院の耳鼻科は非常にアットホームな雰囲気で、日常会話の延長で診療の相談ができるような環境があります。また耳鼻科領域それぞれの専門家が在籍しているため、分からないことはすぐに相談して解決できるところも特徴の一つです。

豊富な症例と充実の指導体制で専門医取得をサポート
当院の耳鼻科で学ぶ一番のメリットは「症例の豊富さ」ではないでしょうか。かぜ症状から腫瘍など幅広い患者さんがいらっしゃいますから、日々の診療の中で得られる知識や経験は、専門医試験の際にも役立つと思います。症例が足りないからと外の病院へ行く必要もなく、上級医のサポートを得ながら早い段階からオペを経験できることも当院ならではと言えるでしょうか。私も専門医試験のときには、ここで学んだ実体験をもとに回答できる問題があったりして、非常に助けられました。症例数が豊富すぎるあまり、慌ただしく感じることもたまにありますけれど(笑)。ハード面・ソフト面ともに充実した病院ですから、「たくさんの症例を経験して質の高い診療の勉強をしたい」という人にはぴったりだと思います。

耳・鼻・頭頸部外科……。サブスペ領域の専門医取得もOK
私は耳鼻科の専門医であると同時に「めまい相談医」として専門外来を担当しています。現在は専門会員を目指して論文作成に取り組んでいるほか、めまいに付随して「頭痛専門医」の資格も取ろうと勉強中です。私の場合は思いがけないご縁から「めまい」を専門にすることになりましたが、もともと診断学が好きだった私には、めまいの原因を特定するプロセスは性に合っているような感じがします。そして何より、自分の治療によって症状が改善すると、患者さんが本当に喜んでくださることが日々の診療の励みになっています。当院は耳・鼻・頭頸部外科の全てを網羅していますから、「まだサブスペが決まっていない」という人も興味が持てる領域を見つけられると思いますし、「これをやりたい!」というものが決まっている人にとっては、より高みを目指せる環境だと思います。

 1日のスケジュール
1日のスケジュール
08:00
~08:20 出勤
08:30
病棟診察など
09:00
午前外来、手術、病棟処置
14:00
午後外来、手術
17:00
病棟診察など
18:00
退勤

精神科
獨協医科大学埼玉医療センター精神科専門研修プログラム
精神科
獨協医科大学埼玉医療センター精神科専門研修プログラム
精神科
獨協医科大学埼玉医療センター精神科専門研修プログラム
幅広い学びを得られる自由度の高い専門研修プログラム。共働き家庭にうれしい「充実の福利厚生」も魅力
イラストレーターから医師へ。異色の経歴をもつ赤松先生は、精神科の医師であると同時にプライベートでは優しいパパの一面もあります。専門研修プログラムを選ぶにあたっては「福利厚生の充実ぶりも決め手になった」と話す赤松先生に、獨協医科大学埼玉医療センターならではの魅力を伺いました。
取材日:2025年2月
更新日:2025年03月
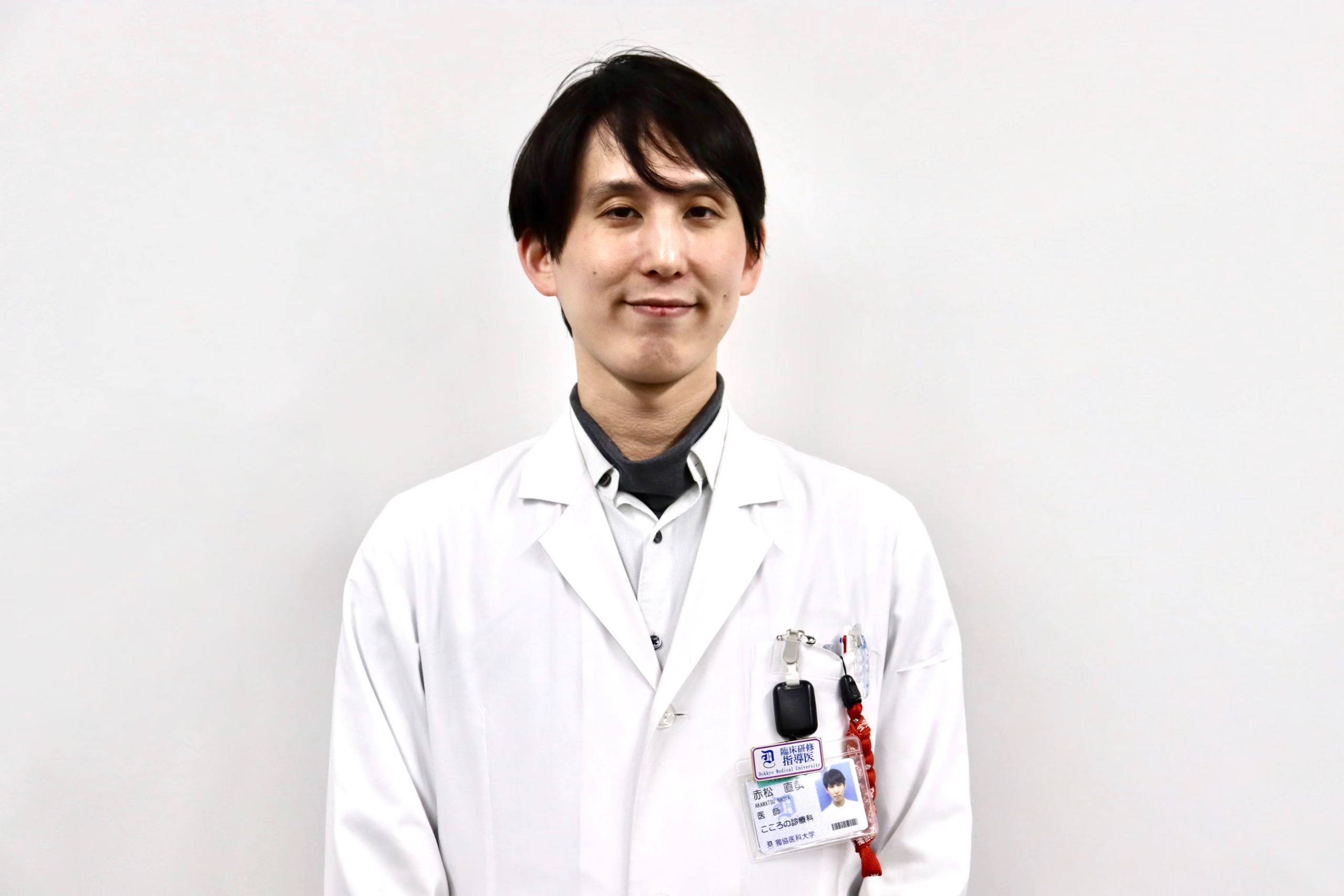
赤松 直哉あかまつ なおや
都市型の大学病院で、幅広いキャリアパス
医師期間
専攻医4年目(医師10年目) ※取材当時
出身大学
旭川医科大学 2016年卒
お住まい
駅徒歩5分、家族と同居、住居手当あり
将来の目標
進路・就労に悩む若い人向けの本が書けたらなと
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
共働き&子育て中の専門医取得を支えた「充実の福利厚生」
私はもともとイラストレーターをしていて、企業から依頼を受けてアプリのイラストを描いたりしていました。その後思うところあって医師を目指し、旭川医科大学を再受験して32歳で医師になりました。初期研修中に結婚して子どもにも恵まれましたが、実家は愛媛県なので両親のサポートは期待できません。妻も仕事をしているなかで専門医を目指すことになったのですが、何とか無事に専門医を取れたのは当院ならではの手厚いサポートのおかげと言えるでしょう。特に、敷地内にある院内保育室(きの子保育室)の存在は非常に大きかったです。きの子保育室では生後2カ月から、夜間や日曜日も子どもを預かってもらえるので、夜勤のときなども安心でした。またほかの病院で勤務する場合や、業務上必要な講習会に参加するときにも預かってもらえたので本当に助かりました。

幅広い学びを得られる自由度の高い専門研修プログラム
私はプログラムの全工程を終えて専門医を取ったばかりですが、本プログラムでは必要症例を典型例で経験できることができました。また興味があれば、産業医、学校医、自治体での厚生相談業務、保健所での自動思春期相談業務、開業医クリニックでの外来などを幅広く経験できます。標準的には3年間で精神科専門医と精神科指定医の症例を集められるようにプログラムスケジュールを組んでいきますが、ライフイベントを重視して産休・育休を取ることなども可能です。このように当院のプログラムは自由度が高いところがメリットではあるものの、自分なりに「こうしたい」というものがないと、ただ何となく時間が過ぎてしまう可能性もあります。さまざまなメリットがある恵まれた環境に甘えずに、きちんと目標設定して取り組む必要があるかもしれません。

キャリアもプライベートも大切にしながら、夢を実現できる環境がある
私はすでに精神科専門医と産業医の資格を持っていて、次は指定医を目指す予定です。また最近は不登校のお子さんが増えていたり、病気休業後の就労支援に関わるニーズが高まったりしていますから、その辺りの学びを深めて支援活動に携われたらいいなと思っています。私はもともとイラストを描いたり文章を書いたりするのを仕事にしていたので、不登校や発達障害の患者さんの就労支援などをテーマにした本を出したいという希望もあります。当院ではそういったことも応援してくれるような風土があるので、その点もとてもありがたいです。専攻医それぞれが叶えたいキャリアプランやライフプランを実現できる施設だと思いますので、恵まれた環境で学び、夢を実現してほしいなと思います。研修医や医学生はもちろん、「これをやりたい!」という熱い思いがある人は、ぜひ見学にいらしてください。
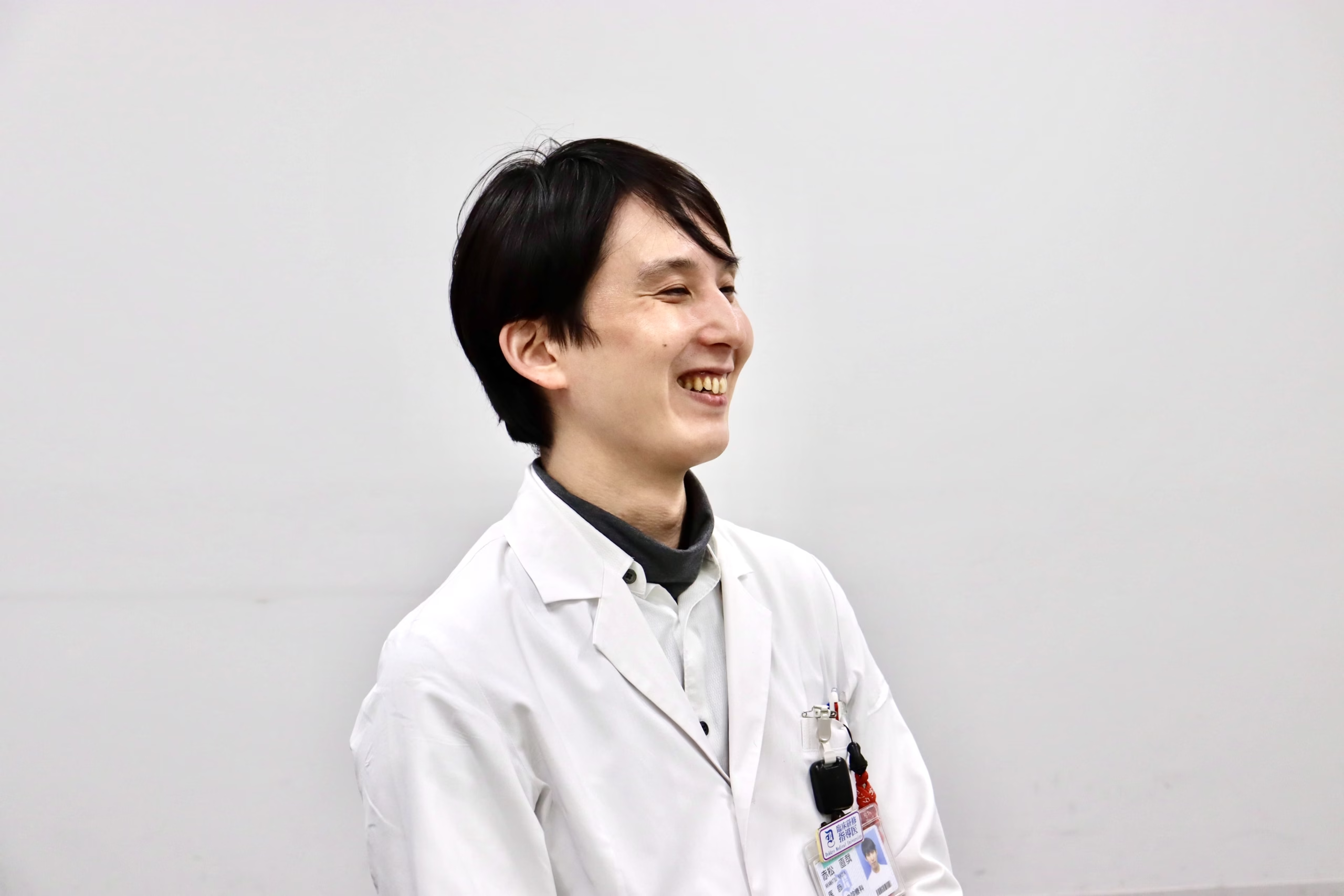
 1日のスケジュール
1日のスケジュール
08:20
出勤
8:30の朝カンファレンスに合わせて出勤
08:30
朝カンファレンス
専攻医、研修医からの症例相談が中心
09:00
午前業務
外来(週3)またはリエゾンチームでの病棟対応(週1)
12:00
昼休み
2025年に建ったばかりの綺麗な食堂があります。
13:00
午後業務
他科病棟からの相談依頼に対応
16:00
勉強会
17:00
退勤
 経験症例
経験症例

外科
獨協医科大学埼玉医療センター外科専門医養成プログラム 指導医
外科
獨協医科大学埼玉医療センター外科専門医養成プログラム 指導医
外科
獨協医科大学埼玉医療センター外科専門医養成プログラム 指導医
専攻医1年目から執刀医に! 外科専門医からサブスペ領域まで、一人一人の未来をサポート
外科志望の若手医師が減少傾向にあるなか、「人のあたたかさに触れられることこそが外科医の魅力」だと語る吉富先生。獨協医科大学埼玉医療センターの外科で診療部長を務め、後進の指導に情熱を注ぐ吉富先生に、同院ならではの魅力を伺いました。
取材日:2025年08月
更新日:2025年10月

指導医 吉富 秀幸よしとみ ひでゆき
当科は消化器外科を中心に診療を行っています。上部、下部、肝胆膵のグループに分かれ診療を行っていますが、全グループ一丸となった体制ですので、いろいろな経験が出来ると思います。特に若い医師が多く、活気にあふれています。加えて、我々の担当する埼玉県東部地区医療圏はまだまだ人口も増えており、地域の医師会からも多くの紹介を頂いて、手術数は年間1,100件を越えています。 特に若い先生方にも多くの手術経験を積んでもらうことを目標に診療を行っております。 ロボット手術など先端の医療を積極的に取り込んでいますし、また、一方で、他院ではなかなか手術が厳しいといわれる進行悪性腫瘍に対しても、できる限り手術を行うことを念頭に、いろいろな手段で患者さまの治療に向き合っております。昨今、外科医不足が叫ばれておりますが、やはり自らの手で患者さまに向き合っていくという当科の診療はやりがいがあふれており、教室員一同で、そのような若いやる気のある医師を教育していくことを目標としています。是非、見学等、いつでもお待ちしておりますので、おいで下さい。
医師期間
医師35年目 ※取材当時
出身大学
千葉大学、1990年(H2)卒
経歴
1990年 千葉大学医学部卒業
1990年 千葉大学医学部 第一外科(現 臓器制御外科学)入局
1991~1994年 前期研修
1994~1998年 千葉大学医学部大学院 (外科学第一) 在籍
1999年 Postdoctoral Associate (Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, USA) 在籍
2003年 千葉市立青葉病院 主任医長
2004年 千葉大学医学部附属病院 肝胆膵外科
千葉大学大学院医学研究院 臓器制御外科学 助手
2013年 千葉大学大学院医学研究院 臓器制御外科学 講師
2017年 千葉大学大学院医学研究院 臓器制御外科学 准教授
2020年 獨協医科大学埼玉医療センター 外科(肝胆膵外科) 主任教授
認定
日本外科学会(専門医、指導医、代議員)
日本消化器外科学会(評議員、専門医、指導医)
日本肝胆膵外科学会(評議員、肝胆膵高度技能指導医)
日本膵臓学会(評議員、理事)
日本消化器病学会(専門医)
日本胆道学会(評議員、指導医)
日本肝臓学会
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
充実した設備とサポート体制のもとで、専攻医1年目から執刀医に!
約900床を有する当院では、最先端の医療に携わることができます。私が診療部長を務める外科では「DaVinci Xi」「hinotori」という2台の手術支援ロボットを導入し、埼玉県内でもトップクラスの手術件数を誇ります。専攻医の先生方にも1年目から積極的に手術を経験していただいており、胆嚢摘出術や鼠経ヘルニアなどから始めて、肝切除や腹腔鏡手術へと段階的にステップアップしていきます。消化器領域では年間1,100件を超える手術実績がありますが、そのうち約3分の1は専攻医に執刀していただいているでしょうか。手術は外科医が1人でするものではありませんが、他の診療科との垣根が低いことも当院の特徴です。術前検査から術後管理に至るまで、各科の先生方と密に連携しながら、スムーズに診療を進めることができます。設備面・人材面ともに恵まれた環境のなかで多くのことを学び、成長できる環境が整っていることが強みです。

外科専門医からサブスペ領域まで、一人一人の未来をサポート
本プログラムに参加した専攻医には、外科専門医の取得はもちろん、その先にある消化器外科領域のサブスペ資格にも挑戦してほしいと思っています。たとえば、日本肝胆膵外科学会の高度技能専門医や、日本内視鏡外科学会の技術認定などです。まずは消化器全般の手術に対応できるスキルを身につけ、そのうえでさらなる専門性を磨いていただきたいと考えています。また臨床に取り組むだけでなく、アカデミックな視点を持つ医師を育てたいとの思いから、学会発表や研究論文の執筆などにも力を入れています。大学院への進学も推奨し、学術的な視点も持った医師の育成を目指しています。臨床と研究活動を両立させるのは容易なことではありませんが、だからこそ指導医である私たちが、その意義を丁寧に伝えながら、忙しさのなかにある喜びや楽しさを感じてもらえるようにサポートしたいと考えています。女性医師のライフステージの変化に柔軟に対応すると同時に、1人の医師に過度な負担がかからないようワークライフバランスにも十分な配慮をしていきたいと思います。

人のあたたかさ・やりがいを実感できる。それが外科の魅力
外科は患者さんの命に直結する診療科であり、医師と患者という立場を超えて「人」として向き合える点に大きな魅力があります。私自身も患者さんとの交流を通じて成長できたと感じていますが、その一方で「命を預かる責任」は非常に大きなものがあります。手術中に想定外の事態が起こるのではないか、プライベートが犠牲になるのではないか……そうした理由から外科を敬遠する方も少なくないでしょう。しかし私が研修医だった頃に比べると、外科医の働き方は確実に改善されてきています。たとえば私が所属する肝胆膵チームでは、6-7人のスタッフが1つのチームになって、約30人の患者さんをチームとして全員で担当します。なので、1人の医師に負担が過度にかからない用にしています。働きやすく学びの多い環境を整え、1人でも多くの外科医を育てることが今の私の使命です。外科だからこそ感じられる人のあたたかさ、そして大きなやりがいのある当科に、ぜひ見学にいらしてください。

 1日のスケジュール
1日のスケジュール
08:00
出勤
月・木 朝カンファレンス
08:30
病棟回診
08:45
手術
適宜 外来・検査・病棟業務
日中の業務は日によって異なる
16:00
病棟回診
月 夕方カンファレンス
17:10
~20:00 退勤
手術などによって退勤時間が遅くなることがある

放射線科
獨協医科大学埼玉医療センター放射線科領域専門医研修プログラム 指導医
放射線科
獨協医科大学埼玉医療センター放射線科領域専門医研修プログラム 指導医
放射線科
獨協医科大学埼玉医療センター放射線科領域専門医研修プログラム 指導医
幅広い経験を積める恵まれた環境のもと、思いやりと責任感あふれる放射線科医を育成
東京医科歯科大学(現・東京科学大学)を卒業後、「中央診療部門で力を試したい」との思いで母校の放射線科に進んだ久保田先生。現在は獨協医科大学埼玉医療センターの放射線科で診療部長を務める久保田先生に、同院の魅力や放射線科医としてのやりがいを伺いました。
取材日:2025年08月
更新日:2025年10月

指導医 久保田 一徳くぼた かずのり
専門研修プログラムを選び、専門医を取得することは一つの節目ですが、それはさらなる飛躍への土台です。 多様な働き方ができ、仲間と支え合える環境を選び、診療・研究・教育に挑戦し続けることを期待しています。
医師期間
医師28年目 ※取材当時
出身大学
東京医科歯科大学(現・東京科学大学)、平成10年卒
経歴
平成10年7月 東京医科歯科大学(現・東京科学大学)医学部附属病院放射線科 医員採用
平成16年3月 東京医科歯科大学(現・東京科学大学)大学院医歯学総合研究科 学位取得卒業
平成29年7月 東京医科歯科大学(現・東京科学大学)医学部附属病院放射線診断科 准教授
平成31年4月 獨協医科大学病院放射線部 教授
令和 3 年4月 獨協医科大学医学部・埼玉医療センター放射線科 主任教授
認定
放射線科専門医・放射線診断専門医、核医学専門医、IVR専門医、超音波専門医、乳腺専門医
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
若手医師中心の雰囲気のよさ、充実した指導体制が自慢
自分の専門として放射線科を選んだのは、この領域に大きな可能性を感じたからです。ほかの診療科に比べると、患者さんと直接お話しする機会は少ないかもしれませんが、画像診断から治療まで幅広い症例に携われる点が魅力でした。母校の東京医科歯科大学で経験を積んだ後、ご縁があって2019年に栃木にある獨協医科大学病院の教授となり、2021年より当院で診療するようになりました。着任当時の放射線科には医師が4人しかおらず、私も専攻医と一緒になって懸命に診療していたのをよく覚えています。それから少しずつ人員が増え、現在は専門医や専攻医をはじめとした診断医が20人ほど所属するまでに成長しました。手前味噌かもしれませんが、若手医師が中心の雰囲気のよい医局だと誇らしく思います。
-scaled.avif)
大学病院であり中核病院。幅広い経験を積める恵まれた環境
本プログラムのメリットとしては、大学病院であると同時に地域の中核病院でもあるという恵まれた環境が挙げられます。大学病院ならではの充実した設備のもと、埼玉県東部地域に暮らす約200万人のあらゆる疾患に対応することで、多彩な経験を積むことができます。当科では一般診療から専門領域まで幅広く学ぶことができ、さらに関連施設での研修も可能ですから、専攻医の先生方にとっても大きなメリットになるでしょう。専攻医の指導を担う医師はもちろんおりますが、私自身も午前と午後の2回は現場に顔を出し、診療上の疑問や研究活動に関する相談に応じています。スタッフ一人一人がお互いを尊重し、興味のあることを思う存分追求できる土壌があること、それが一番のアピールポイントかもしれません。
-2.avif)
思いやりと責任感を持って仕事ができる医師に成長してほしい
放射線科医としてのキャリアにはいくつかのパターンがあり、大学院で研究に取り組むこともできれば、臨床医として地域医療に携わる道もあります。また、診断専門医の資格があれば、在宅で仕事を続けることも可能です。出産や子育てといったライフステージの変化に応じて柔軟に働き方を調整できるのも、放射線科の魅力の1つかもしれません。専攻医の先生方は1日25件前後の読影を目指して欲しいと思っていますが、これは決してノルマではありません。放射線科では「思いやりと責任を持って仕事をする」という理念を掲げており、子育て中や論文執筆中のスタッフを進んでサポートする雰囲気があります。お互いを思いやる心にあふれた、本当に人柄のよいスタッフばかりですから、ぜひ私たちの仲間になっていただけたらうれしいです。

 1日のスケジュール
1日のスケジュール
08:45
出勤
09:00
読影、検査指示
ローテートによってはIVRや超音波
12:00
昼休憩
13:00
医局での作業、研究や調べもの
14:00
読影
ローテートによってはIVRや超音波
16:00
指導チェック
上級医が適宜レポートチェックしてくれるが、直接の指導も受ける
17:00
自己研鑽
18:00
退勤

小児科
獨協医科大学埼玉医療センター 小児科専門医養成プログラム 指導医
小児科
獨協医科大学埼玉医療センター 小児科専門医養成プログラム 指導医
小児科
獨協医科大学埼玉医療センター 小児科専門医養成プログラム 指導医
教え合い、支え合う――。小児科専門医からサブスペまで幅広い学びをサポート
小学生のときに1型糖尿病を発症して入院。自らの闘病生活をきっかけに、小児科医を志したという髙谷先生。現在は獨協医科大学埼玉医療センター 小児科の診療部長を務める髙谷先生に、プログラムの特色や同院ならではの魅力を伺いました。
取材日:2025年08月
更新日:2025年10月

指導医 髙谷 具純たかたに ともずみ
当科では、皆さんが「患者中心の医療」と「専門性の深化」を両立できるよう、多彩な研修プログラムを整えています。初期段階では、幅広い小児疾患への対応力を養い、その後は希望に応じて各専門分野の診療・研究にも積極的に関わることができます。 指導医は小児科専門医に加え、内分泌代謝、アレルギー、膠原病、新生児、神経などのサブスペシャリストで構成されており、個別のキャリア相談にも対応しています。「まずはジェネラルな力をつけたい」「将来は大学院進学や留学も視野に入れている」など、多様な志向に応じた柔軟な研修が可能です。 教育面では、「教え合い、支え合う文化」を大切にしており、病棟・外来・カンファレンスでの活発な意見交換が日常的に行われています。 失敗を恐れず、疑問を共有しながら共に成長できる、温かな学びの環境が整っています。
医師期間
医師23年目 ※取材当時
出身大学
千葉大学、2003年卒
経歴
2003年3月 千葉大学医学部卒業
2011年3月 千葉大学大学院医学薬学府博士課程修了
2012年4月 ジョスリン糖尿病センターリサーチフェロー(Rohit N.Kulkarni教授)
2015年7月 千葉大学医学部附属病院 小児科 助教
2022年10月 千葉大学大学院医学研究院 小児病態学 助教
2023年4月 千葉大学大学院医学研究院 小児病態学 講師
2024年7月 千葉大学医学部附属病院 小児科 診療准教授
2025年4月 獨協医科大学埼玉医療センター 小児科 主任教授
認定
小児科専門医・指導医、内分泌代謝科専門医・指導医、糖尿病専門医・指導医
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
患者から小児科医へ。1型糖尿病治療をきっかけにキャリアを築く
私が医師を目指したのは、小学2年生のときに1型糖尿病を発症したことがきっかけでした。3週間の入院加療を経て、その後も毎月の通院を続けながら現在に至ります。当初は今のように多様なデバイスがなく、毎日悪戦苦闘しながら生活していたのを覚えています。多くの医療者の方々に支えていただくなかで、将来は自分が患者さんを支える側になりたいと考えるようになりました。そして、1型糖尿病を抱えながら医師になられた女性医師の存在を知り、この道を志すことを決意したのです。千葉大学医学部を卒業後は、20年以上にわたって母校の小児科に所属し、世界最高峰とされるジョスリン糖尿病センターに留学した時期もありました。その後ご縁があって2025年4月に当院へ赴任し、若くて活気あふれる小児科教室で教授を務めています。
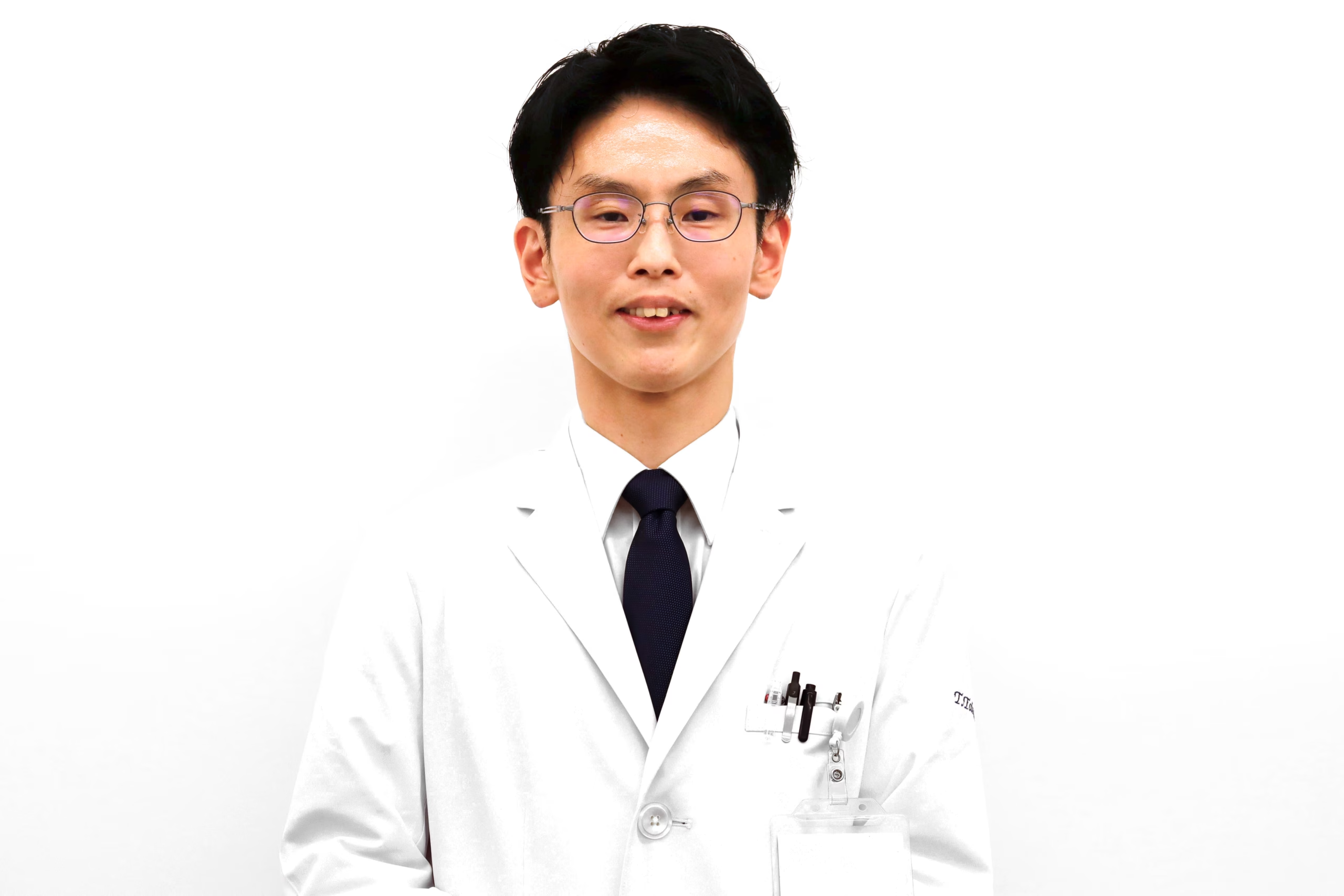
医師・コメディカルともに充実。働きやすい環境も魅力の1つ
当院は埼玉県にありますが、都心からのアクセスがよく、若い先生方にたいへん人気のある研修施設です。小児科には私を含めて約20人の医師が所属しており、非常に活気にあふれています。近年は研修医や専攻医の先生方が続々と入局してくださっているため、同世代の先生から指導を受けられる機会も多く、教室全体の総合力がさらに高まっているように感じます。また、医師だけでなくコメディカルも充実しており、働きやすい環境が整っていることも特徴の1つです。当直の医師にきちんと申し送りをすれば、帰宅が遅くなることはほとんどなく、オンとオフをしっかり切り替えてメリハリのある働き方が可能です。プライベートを大切にしたい方にとっても、安心して働ける環境ではないでしょうか。
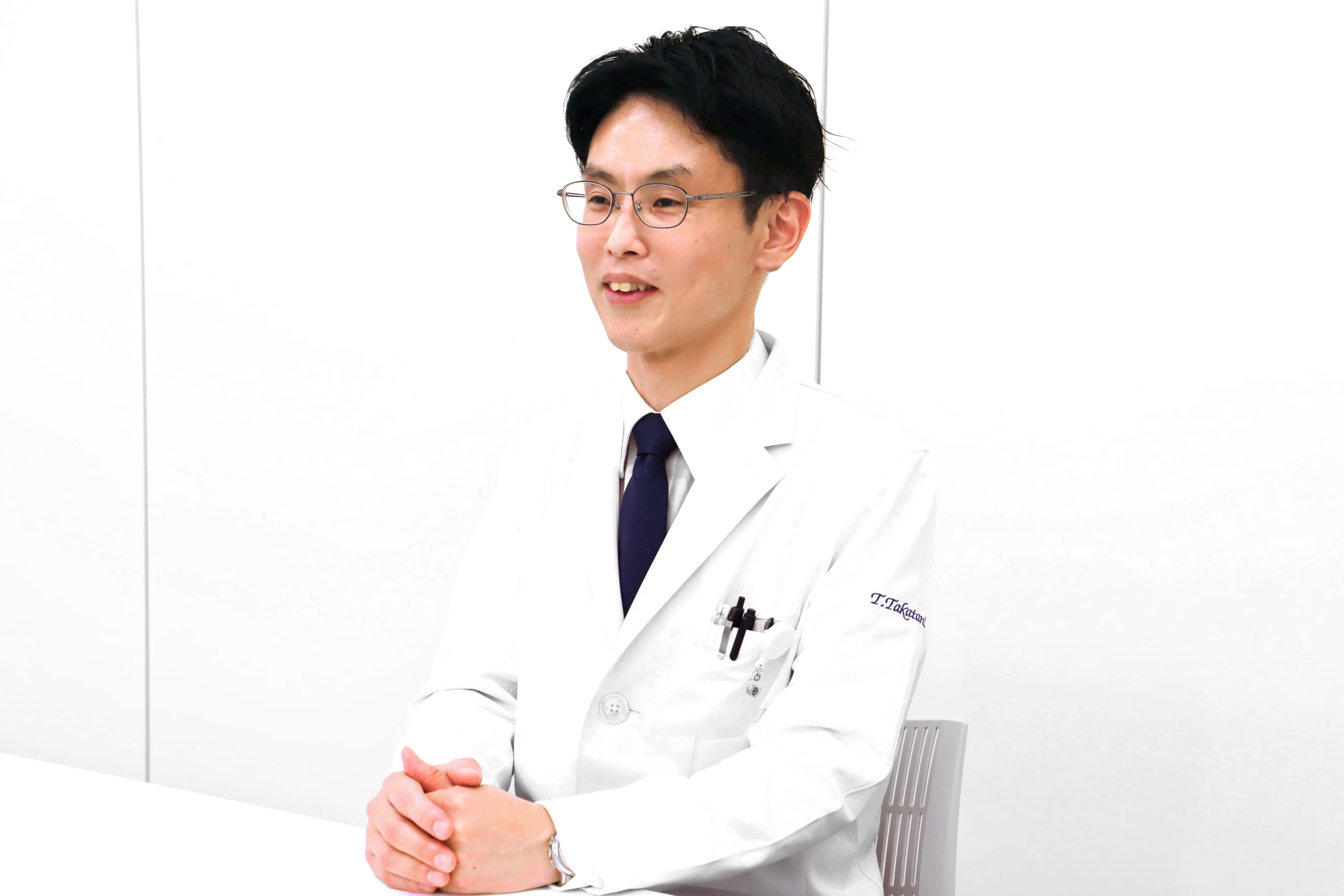
小児科専門医からサブスペまで。教え合い、支え合い、幅広い学びをサポート
本プログラムは「患者中心の医療」と「専門性の深化」の両立を実現できる内容になっており、専攻医1年目に小児疾患を幅広く学んだ後、一人一人の希望に応じて専門性を磨くことが可能です。小児科専門医を取得後に、小児神経、内分泌代謝、アレルギーといったサブスペ領域の専門医を目指す先生もおられ、そのための学びの場を十分にご提供できる環境があります。毎日朝夕にカンファレンスを行うとともに、週に1度は2時間ほどかけて全体カンファレンスを開き、その中で論文の抄読会も実施しています。「教え合い、支え合う文化」のある医局ですから、失敗を恐れずに大きく成長していただきたいと思います。私たちが皆さんの成長をしっかりとサポートいたします。

 1日のスケジュール
1日のスケジュール
08:15
出勤
08:30
モーニングカンファレンス
救急外来患者、入院患者の申し送り
09:00
病棟・一般外来・外来処置
病棟患者の診察・処置、外来診察・処置
12:00
昼食
13:00
病棟・一般外来・外来処置
病棟患者の診察・処置、外来診察・処置
15:00
教授回診(木)・勉強会/抄読会(木)
木曜日に教授回診でプレゼンテーション、その後勉強会/抄読会があります。
17:15
イブニングカンファレンス
入院患者の申し送り
17:30
退勤
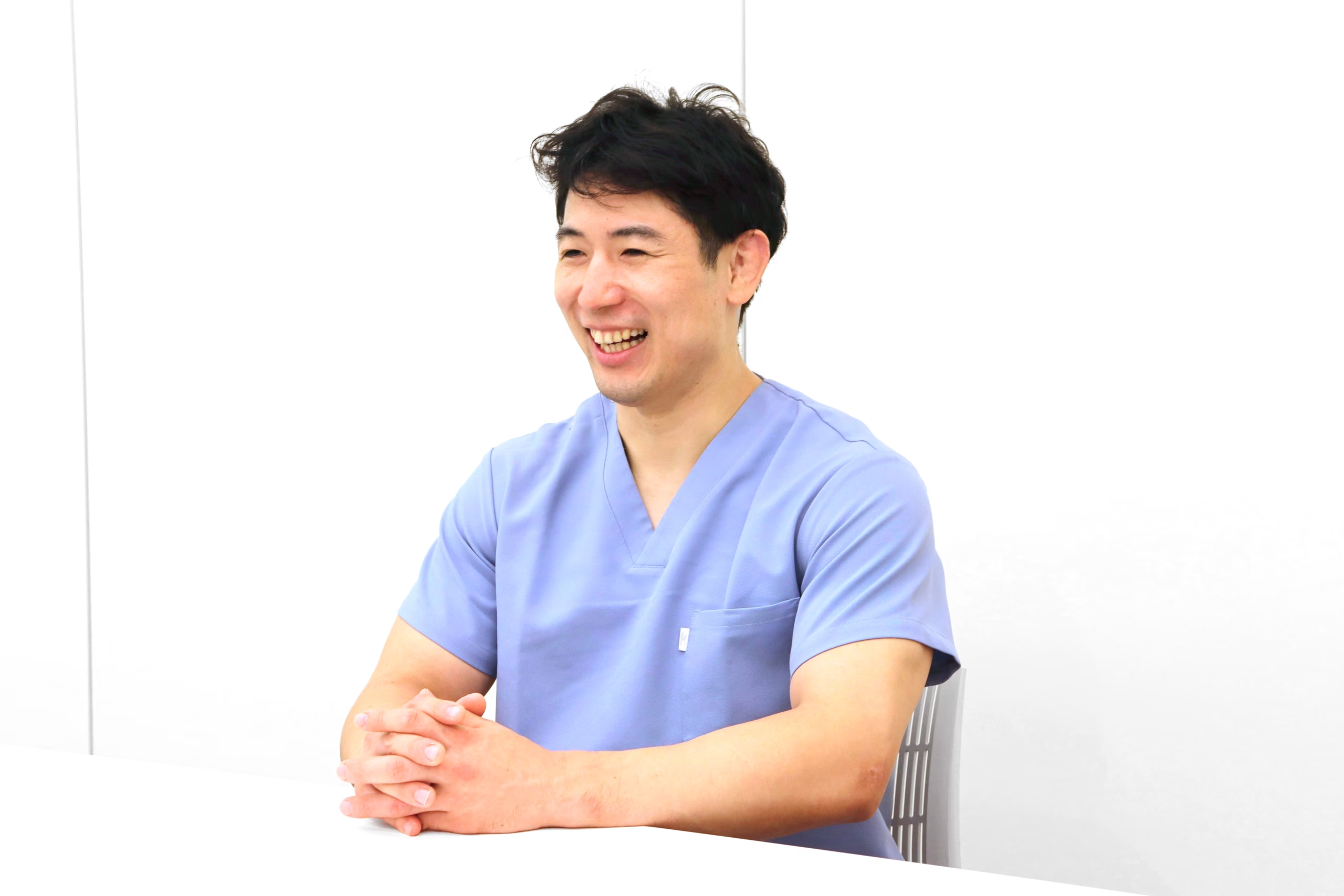
整形外科
獨協医科大学埼玉医療センター整形外科専門医養成プログラム 指導医
整形外科
獨協医科大学埼玉医療センター整形外科専門医養成プログラム 指導医
整形外科
獨協医科大学埼玉医療センター整形外科専門医養成プログラム 指導医
「最先端の学び」と「働きやすさ」を両立。豊富な症例数で整形外科専門医を目指す!
医師であり柔道家でもある簗瀬先生は、スポーツ整形外科医を目指してこの道に進んだと言います。東京オリンピック・パラリンピックの柔道スポーツドクターも務めた簗瀬先生に、獨協医科大学埼玉医療センターならではの特色やプログラムの魅力などを伺いました。
取材日:2025年08月
更新日:2025年10月
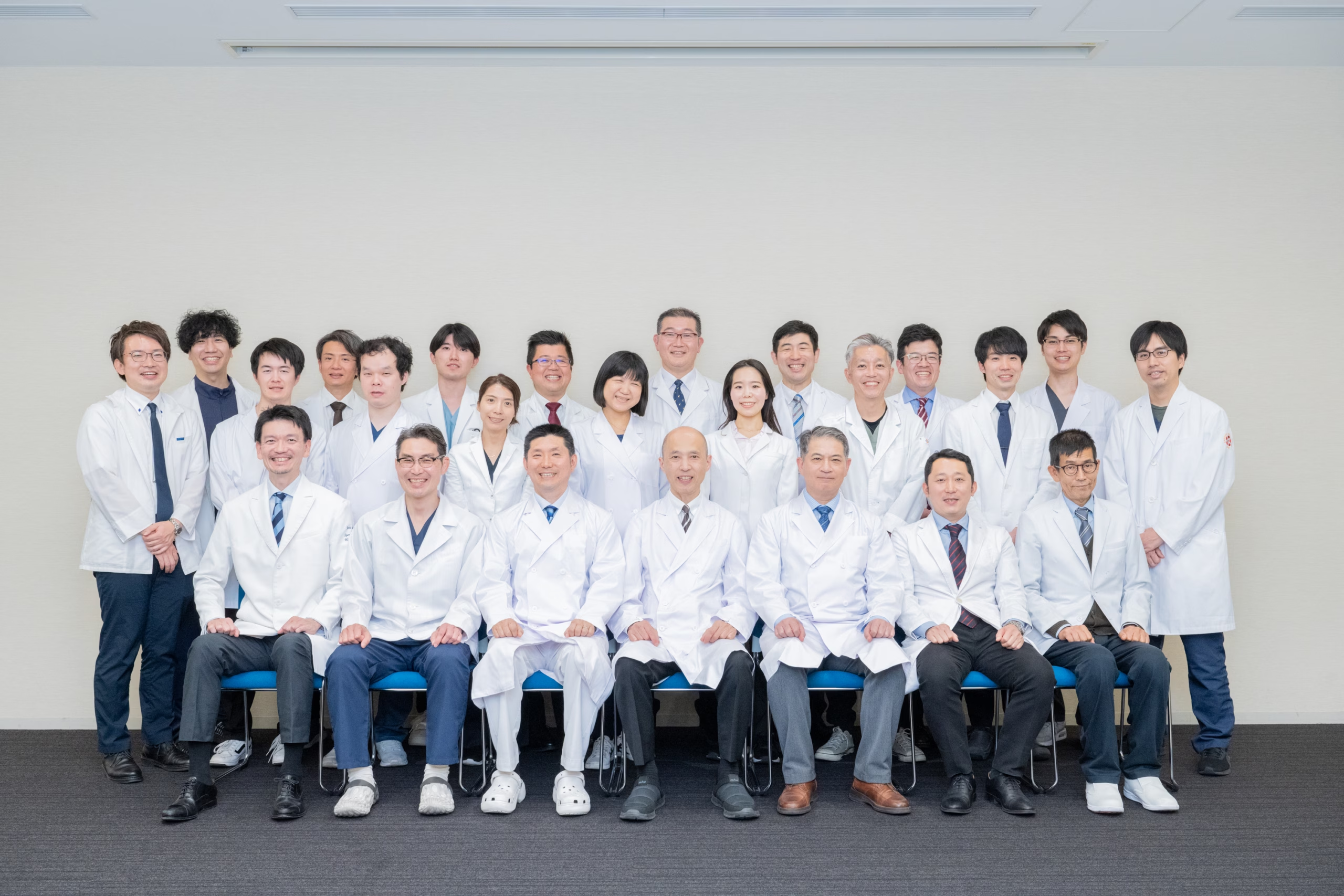
指導医 簗瀬 司やなせ つかさ
本プログラムでは病院の垣根なく連携して、専攻医を見守り、成長を支えております。 実際に専攻医の先生たちはすべての運動器疾患について基本的・応用的・実践的能力を有し、安全で質の高い運動器医療を提供できる整形外科専門医になっております。 是非一度見学にいらして下さい。
医師期間
医師11年目 ※取材当時
出身大学
獨協医科大学、2015年卒
経歴
2015年 太田西ノ内病院 初期研修医
2017年 獨協医科大学埼玉医療センター整形外科
2018年 流山中央病院
2019年 済生会栗橋病院
2020年 獨協医科大学埼玉医療センター救命救急センター
2021年 獨協医科大学埼玉医療センター整形外科
認定
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医
日本スポーツ協会公認スポーツドクター
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
専攻医から指導医へ。自らの経験を踏まえ、一人一人の学びをサポート
私は学生時代から柔道を続けていて、今も全日本医師柔道大会などに出場することがあります。練習中にけがをすることも少なくありませんでしたから、スポーツ整形を専門にしたいと考えて当院の専攻医となり、整形外科専門医を取りました。私が当院のプログラムを選んだのは、「獨協医科大学出身であることが大きな理由です。当院の整形外科は私が専攻医だった当時から人気の医局でしたし、以前に比べると募集定員も増えてきています。現在は私も、学ぶ側から教える側へ立場が変わりましたが、専攻医だった頃の先輩方を見習い、相談しやすい雰囲気づくりを心がけているつもりです。手術前のカンファレンスなどでしっかりとした指導を行い、専攻医の皆さんの学びをサポートしたいと考えています。
多様なキャリアプランに対応する「最先端の学び」を提供
当院の整形外科は、大きく4つのグループに分かれています。私が所属しているのは脊椎グループで、そのほかに股関節、膝関節、手と足のグループがあります。整形外科では全体で行う週に1度のカンファレンスに加え、各グループでも週に1度のカンファレンスがあります。手術件数は所属するグループによって異なりますが、専門医の取得に必要な症例はまんべんなく経験できるでしょう。専門医を取得した後は、そのまま大学病院で診療を続けるか、市中病院へ移るか、開業するかなど、さまざまな選択肢があると思います。本プログラムはそうした多様なキャリアに対応できるのが特徴であり、何よりも「最先端の医療」を学べることが魅力と言えるでしょう。
「9時から5時」の勤務で、プライベートもしっかり確保
整形外科では、いわゆる「9時から5時まで」の働き方が可能で、外来や病棟を担当する日は午後5時に帰宅できることがほとんどです。手術日は帰りが多少遅くなることもありますが、それでも午後6時か7時頃までには病院を後にできると思います。プライベートをしっかり確保できる環境ですし、有給休暇も積極的に消化することが奨励されています。専攻医の方が休日に呼び出されるようなことはほぼありませんので、安心していただければと思います。担当する患者数は所属グループによって多少異なりますが、あらゆる運動器疾患について基本・応用・実践的な学びを得られる環境であることは確かです。もし興味のある方がいらしたら、ぜひ一度見学にいらしていただけたらうれしいです。
 1日のスケジュール
1日のスケジュール
09:00
出勤
09:00
~ 外来 病棟業務
入院中の術後の患者さんや院内紹介・救急外来の患者さんを上級医と共に診察します
12:00
~ 昼食
13:00
~ 外来 病棟業務
翌日の手術の患者さんを上級医と共に診察します
17:00
退勤

麻酔科
獨協医科大学埼玉医療センター麻酔科専門医研修プログラム 指導医
麻酔科
獨協医科大学埼玉医療センター麻酔科専門医研修プログラム 指導医
麻酔科
獨協医科大学埼玉医療センター麻酔科専門医研修プログラム 指導医
麻酔科症例を幅広く経験し、学位取得も可能! ワークライフバランスも万全のプログラム
初期研修でさまざまな診療科を経験するなかで、麻酔科の魅力に気付いたという古田先生。「手術中にモニターを見続けることがまったく苦にならない」と話す古田先生に、獨協医科大学埼玉医療センターならではの特色や現在の働き方などを伺いました。
取材日:2025年08月
更新日:2025年10月

指導医 古田 和睦ふるた かずよし
大学院への進学や卒業までのサポートも手厚く、また留学や出向先、サブスペシャリティの選択などの自由度も高いです。 プライベートに関しても非常に理解のある医局なので、興味のある方は是非一度見学にいらしてください!
医師期間
医師8年目 ※取材当時
出身大学
聖マリアンナ医科大学/2018年卒
経歴
聖マリアンナ医科大学卒業/2018年3月
聖マリアンナ医科大学病院初期研修開始/2018年4月
聖マリアンナ医科大学病院初期研修終了/2020年3月
獨協医科大学埼玉医療センター麻酔科専攻医プログラム開始/2020年4月
獨協医科大学埼玉医療センター麻酔科専攻医プログラム修了/2025年3月
獨協医科大学埼玉医療センター麻酔科院内助教/2024年4月~
獨協医科大学大学院(先端外科学)入学/2021年4月
獨協医科大学大学院卒業/2025年3月
認定
日本専門医機構認定麻酔科専門医、日本医師会認定産業医
プログラムスケジュール
プログラム指標※インタビュー対象者の個人の主観です
多様な手技に挑戦できることが麻酔科医の魅力
もともと手技が好きだったこともあり、自分の専門を決める際には麻酔科のほかに、循環器内科や消化器内科も考えていました。その中で麻酔科を選んだのは、気管支ファイバーや中心静脈(CV)カテーテルなど多様な手技に携われる点に魅力を感じたからです。麻酔科医というと、手術中ずっとモニターを見ているイメージがありますが、私の場合はそれがまったく苦にならなかったことも決め手になりました。当院のプログラムは、日本ペインクリニック学会のHPで見つけました。以前からペイン領域に興味を持っていたのですが、学会の名誉会長を務める奥田教授が当院にいらっしゃることが分かり、「ぜひここで学びたい」と思いました。見学させていただいたときの医局の雰囲気もよかったですし、実際に仕事をしていても働きやすさを実感しています。

質・量ともに充実した症例を経験でき、学位取得も可能
当院の麻酔科には私を含めて40人以上の医師が所属し、22室あるオペ室で日々行われる手術に対応しています。大学病院ならではの症例数と幅広さがあり、専門医取得に必要な症例をもれなく経験できることが本プログラムの特徴と言えるでしょう。一方で、4年間の研修期間は原則として当院に勤務するため、「いろいろな病院を見てみたい」という場合は物足りなく感じるかもしれません。ただし、専門医取得後は国内外への留学や学位取得など、さまざまなキャリアパスを選択できます。実際に私も大学院で研究に取り組んでおり、同期の中には海外に留学している友人もいます。もちろん、何をするにも強制されるようなことはなく、自分の興味に応じて自由に学べるところも魅力だと思います。

夏と冬に1週間の有給休暇。ワークライフバランスも万全
麻酔科は毎年5~6人の入局が続いており、同期が8人いる学年もあります。医局の規模が大きいことで、非常に働きやすい環境であることも特徴の1つです。当直明けは必ず帰宅できますし、夏と冬にはそれぞれ1週間ずつ有給休暇を取得できました。医局員がそれぞれ協力し合い、しっかりと時間を区切って働けているので、前向きに仕事に取り組むことができています。昔ながらの大学病院の働き方とは、イメージが大きく異なると思いますし、かなり恵まれた環境だと言えるのではないでしょうか。オンとオフのメリハリがつけやすいので、キャリア重視の方にも、プライベート重視の方にもマッチするプログラムだと思います。興味のある方にはぜひ一度、見学にいらしていただきたいです。

 1日のスケジュール
1日のスケジュール
07:30
出勤
カンファレンスの前までに始業点検や麻酔準備など
08:00
カンファレンス
08:30
手術室業務
12:00
昼休憩
12:30
手術室業務
17:00
退勤




